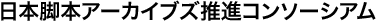1941年4月17日、長崎県諫早市に生まれる。
栄町で呉服店を営む市川家は、明治維新までは島原藩の禄を食む中級士族であった。維新後諫早に移り、呉服商に転業。最盛期は十数人の使用人が賑やかに立ち働く大店だったという。
1941年頃は店の最後の輝きの時代で、市川家にとって待望の跡取り息子の誕生は、太平洋戦争突入前夜の不穏な時期にも拘わらず、一家に手放しの快哉で迎えられた。祖父母、両親の期待と愛を一身に受け大禍なく健やかに育つ。戦中、衣料統制で呉服業は次第に立ち行かなくなり、店はついに休業。父・一郎は、海軍大村航空隊の英語の教官になった。元々、前垂れつけて女子供相手の呉服商が気性に合わなかったので、戦後になって再び呉服屋に戻ることはなかった。カメラ店経営者、印刷会社社長、市議会議員、俳句誌の主宰者(俳号青火として活躍)、家作の家主……等など肩書きが定まることは無かったという。その父のことを「本人は、冗談めいて『俺は何者でもない高等遊民だ』と気取っていたが、案外本気だったのかもしれない」と語っていた。
 小学生の頃から無意識に創作に向かっていく。妹に『千夜一夜』のような物語を話して聞かせたり、画を描くのも得意で、新作を描いて級友に喜ばせていた漫画が地元の新聞に取り上げられたこともある。実家の前にあった映画館では木戸御免で小さい時からよく通ったという。こうしたことは後に脚本家を志す萌芽といえる。
小学生の頃から無意識に創作に向かっていく。妹に『千夜一夜』のような物語を話して聞かせたり、画を描くのも得意で、新作を描いて級友に喜ばせていた漫画が地元の新聞に取り上げられたこともある。実家の前にあった映画館では木戸御免で小さい時からよく通ったという。こうしたことは後に脚本家を志す萌芽といえる。
10歳の頃、母が肺結核となり入院。その見舞いの帰り道、病室の窓から母が力をふり絞って放ってくれた林檎を受けとれず、落としてしまう。間もなく母が亡くなり(享年39歳)、それが最後の邂逅となったことで悔恨が悲しみと相俟ってずっと心に残る。後に執筆した東芝日曜劇場『夢の指環』(’85)の脚本のなかの少女に母が投げた林檎を見事、受取らせることでようやく少しだけ心の荷を下ろせたと語っていた。のちにある作品のタイトルとした『悲しみだけが夢をみる』(ドラマ自体は別の話)は少年期に母を亡くしたさびしさ、侘しさから気持ちを逸らすために夢見がちな少年となった自身の体験そのものの表れであり、全ての作品の世界観に少なからず影響を及ぼしている。
その後、ミッションスクールの鎮西学院中等部に入学、寮生活をはじめる。賛美歌の流れる小高い丘の広い敷地内には牧場や畑があり、緑の中に赤い屋根の校舎、牧舎、サイロや寮が点在した。当時の日本には珍しい西洋的な風景は自身の心の中で原風景になっていると後に語っている。小学生時代の漫画に続いて演劇の脚本を書き始めたことが作家の道への端緒となる。長崎県立諫早高校に移ってからは洋画も見るようになり、中でもフェリーニの『道』に感動。映画へのあこがれが本格的に脚本の創作を学ぶことへ繋がり上京を決意させる。
 1959年に日本大学芸術学部映画学科に入学。1、2年の頃は東宝で映画の「梗概」書きをする。その後、TBSでアルバイト。大学には6年間通い、アルバイトも続けながら、浅草からテレビに進出してきたばかりの萩本欽一やポール牧のコント番組を書き始め、半ば放送作家としての仕事をしながらの学生生活だった。
1959年に日本大学芸術学部映画学科に入学。1、2年の頃は東宝で映画の「梗概」書きをする。その後、TBSでアルバイト。大学には6年間通い、アルバイトも続けながら、浅草からテレビに進出してきたばかりの萩本欽一やポール牧のコント番組を書き始め、半ば放送作家としての仕事をしながらの学生生活だった。
大学卒業後は、はかま満緒門下に入り、テレビ局にアルバイトとして出入りするようになる。コントやバラエティ番組のアイディアや台本を書くがことごとく不採用。はかま氏には「きみのはいつも長過ぎる。ドラマを書いた方がいいんじゃないか」というアドバイスを受けたそうである。
そんなある日、日本テレビのロビーで円谷プロが日本テレビと組んで特撮の新番組『快獣ブースカ』を始めるという話を耳にする。その晩、徹夜でプロットを6本書いて円谷プロへ持ち込む。1966年『快獣ブースカ』第4話「ブースカ月へ行く」で脚本家としてデビュー(25歳)。結局提出したプロットは全て採用され、『快獣ブースカ』のメインライターとなる。それ以降、円谷プロのウルトラマン・シリーズ『ウルトラセブン』『帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマンA』や『コメットさん』などの子供向け番組を多数手掛けた。
1969年、執筆した『マキちゃん日記』に出演していた女優・柴田美保子と出会う。撮影見学の帰路、駅で再会したときに彼女が気を効かせて買い、笑顔で手渡してくれた切符が手放し難かったと語っている。1972年5月31日に結婚。美保子夫人はその後も女優を続ける一方、朝のワイドショーのMCも務めた。多忙ながらも日常のことや経済的なやりくりもさりげなく差配できる人だったので執筆用の貴重な資料となる高価な古書を購入したいときに、いつでも相談なく買うことができたと常々感謝していた。
 30歳を過ぎる頃から次第に大人向けドラマの執筆の機会が増えていく。1974年には、若者に多くの支持を得、いまや伝説とまで言われる『傷だらけの天使』で広くその名を知られるようになり、同年『黄色い涙』でNHK初執筆。1978年には37歳の若さで大河ドラマ『黄金の日日』を執筆する。大河ドラマ史上、初めて為政者ではなく市井の人びとを主人公にした群像劇を活き活きと描き、時代の変わり目に於ける価値観の転換を見事にドラマ化した。また当時TVでは無名に等しかった根津甚八、川谷拓三等の魅力を引き出し、その後のブームのきっかけを作った。『黄金の日日』はその後戯曲化して大谷竹次郎賞を受賞。
30歳を過ぎる頃から次第に大人向けドラマの執筆の機会が増えていく。1974年には、若者に多くの支持を得、いまや伝説とまで言われる『傷だらけの天使』で広くその名を知られるようになり、同年『黄色い涙』でNHK初執筆。1978年には37歳の若さで大河ドラマ『黄金の日日』を執筆する。大河ドラマ史上、初めて為政者ではなく市井の人びとを主人公にした群像劇を活き活きと描き、時代の変わり目に於ける価値観の転換を見事にドラマ化した。また当時TVでは無名に等しかった根津甚八、川谷拓三等の魅力を引き出し、その後のブームのきっかけを作った。『黄金の日日』はその後戯曲化して大谷竹次郎賞を受賞。
1981年『港町純情シネマ』『チャップリン暗殺計画』で芸術選奨文部大臣新人賞を受賞。1982年『淋しいのはお前だけじゃない』で既成のドラマとは異質の虚実入り交じった独特の世界観を描き、第一回向田邦子賞を受賞。
それ以降も「夢」「聖と俗」「原罪」「メメント・モリ(死を忘れるな)」などをテーマに多くのドラマを執筆していく。「東芝日曜劇場」、また当時「お嫁さんにしたい女優ナンバーワン」だった竹下景子に風俗嬢を演じさせてあっと言わせた、人気シリーズ「モモコ」や数々の連続ドラマ、TV各局の開局記念ドラマなどの脚本を執筆した。作家としての韜晦を楽しむことを信条に、「同じことは二度とやらない」と自らに課して毎回新たなものに挑戦し、またジャンルを隔てる壁を乗越えようと意図し、舞台、映画、小説にも活動のフィールドを拡げた。
1988年芸術選奨文部大臣賞(『明日1945年8月8日・長崎』『もどり橋』『伝言』)1999年モンテカルロ・テレビ祭最優秀脚本賞(『幽婚』)など、国内に留まらず海外での賞にも輝いた。初めての映画、『異人たちとの夏』(脚色)で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。
 また大河ドラマ『山河燃ゆ』『花の乱』などの歴史ドラマ執筆の際には膨大な資料を集め、詳細な調査研究を厭わなかった。自身の出身地である長崎への深い郷土愛から、天正の少年使節、天草の乱、江戸時代後期の長崎の歴史的役割などに造詣が深く、そのことが小説『蝶々さん』『幻日』の執筆につながる。旺盛な執筆活動の傍ら、テレビにも多く出演し、脚本家の社会的認知度を高めた。
また大河ドラマ『山河燃ゆ』『花の乱』などの歴史ドラマ執筆の際には膨大な資料を集め、詳細な調査研究を厭わなかった。自身の出身地である長崎への深い郷土愛から、天正の少年使節、天草の乱、江戸時代後期の長崎の歴史的役割などに造詣が深く、そのことが小説『蝶々さん』『幻日』の執筆につながる。旺盛な執筆活動の傍ら、テレビにも多く出演し、脚本家の社会的認知度を高めた。
社会的な活動として、社団法人日本放送作家協会理事長(その後は会長)を長くつとめ、文科省中教審や文化庁国民文化祭、BPO放送倫理検証委員会の委員、そして故郷でも長崎歴史文化博物館長等を歴任。特にアジアドラマカンファレンスでは、創設者の一人として、アジアで活躍する脚本家・制作者が語り合う国際会議を開催し、放送文化の相互理解に貢献した。
また「散逸するのが当たり前」とされていた放送台本や脚本のことを憂い、「遺すという考え方がないものは文化とは言えない」と日本脚本アーカイブズの創設運動の先頭に立って脚本・台本の保存に奔走し、文化庁と国立国会図書館との協定を成立に導いた。
2011年10月、肺炎のために入院。精密検査の結果、肺癌と判明する。自らの死生観に従い、痛み止め措置以外の点滴を含む一切の治療を拒否する。11月初旬に旭日小綬章受章。病が重篤であることを周囲には知らせず、自らの原作をドラマ化した『蝶々さん —最後の武士の娘—』のNHKでの完成試写会には病を押して出席し、「この歳になると、一作一作が遺作のつもりでやっている。作品によってはこれが遺作になっては嫌だなと思ったりする。今日この作品を拝見して、こういう作品が生涯の遺作になれば幸運だなと思ったりしました」と語った。
12月10日朝、永眠。享年70歳。
*集められた資料は長崎県諫早市立図書館の「市川森一シナリオルーム」に展示されている。
シナリオルームの本棚は、生前自らが並べた通りの形で保存されている。
*プロフィール作成は市川森一氏の実妹・由実子さんにご協力頂きました。