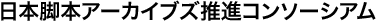市川森一
 「月刊ドラマ」閲覧室
「月刊ドラマ」閲覧室
- 1994年5月号
第1回 二人の日野富子に出会うまで - 1994年6月号
第2回 歴史ドラマの人物設定 - 1994年6月号
第3回 資料とシナリオハンティング - 1994年9月号
第4回 二つの悩みとスタッフ・俳優の熱意 - 1994年12月号
第5回 登場人物の交替から 最終回を書き上げるまで(最終回)
1994年5月号
第1回 二人の日野富子に出会うまで
室町時代は現代と似ている
――今回の大河ドラマはオリジナルですが、題材については全くゼロから始まったのですか?
「いえ、最初は原作が四本くらい候補にあげられていました。いずれも歴史小説で、戦国時代の話でした。その段階で制作サイドでぜひこれをというのがなかったんですね。帯に短しタスキに長しということで。一応こういう企画が出ているが、さらに積極的にやりたいものがあれば意見を聞きたいということでした。
僕は、漠然と室町時代がいいんじゃないかなアと思ってたんです。一つは、大河ドラマでまだ室町をやってないということもありました。それと、時代感覚が現代と室町ととても似た面があるんじゃないか、混沌としている。だから、室町の場合は大河ドラマのヒーローあるいはヒロインが、なかなか見つかりにくい。室町時代で、われわれが教科書で知ってるのは初代の尊氏はともかくとして足利義満、世阿弥、一休さんくらいしかいない。室町を舞台にしたいと言っても、誰を主人公にするのかと突っ込まれた時に、「誰」とすぐ応えられないといけないと思って、その日の会議の前に、バラバラと室町の人物事典を見た、そこで日野富子という名前が目に止まったんですね。
日野富子は、夫の義政を尻に敷いて、まつりごとをほしいままにした悪女だという印象しかありませんでしたし、僕が読んだ人物事典にもそういうことしか書いてありませんでした。これは、ますます現代と共通するヒロインが出来るな――つまり、悪女という烙印をおされている女性を、本当に彼女が悪女だったのかどうだったのか、彼女を悪女たらしめた時代背景というものが、必ずそこにあるはずだし、悪女というニュアンスこそまさに、現代に通じる。<女の時代>という意味もありますけど、現代人の視点で彼女を見た時に、それはどう写るのかを一つテーゼとして置いて、意義のあるものになるかもしれない。その会議の席上で日野富子はどうだろうか、という話をやや熱っぽく語ってみたんです」
日野富子の実像を探る
「次の会議では、それでは、日野富子が大河ドラマの主人公として成り立つ人物であるかどうか、日野富子を主人公にしてどんなストーリー構成が考えられるのか、企画書にまとめてみてくれということになりました。そういう宿題を課せられましたんで、今、日野富子を扱う意味と、僕流の解釈による日野富子像と彼女を主人公にしたストーリーはざっとこうなると作ってみました。
日野富子の人物像については、悪女として後世に伝えたものは、『大乗院寺社雑事記』興福寺の尋尊という坊さんの日記だけということが分かったので、富子の実像はまだ他にあると。その実像をさぐることは、歴史ドラマの興味にもつながる。ドラマ展開の上ではサスペンスの要素も入るので、きわめてドラマチックな人物像が作りあげられる。
現に、富子が悪女と言われた原因というのは、<女だてらに>経済活動を活発にしたこと。ただ、その背景には、室町時代の風土を無視することは出来ない。室町時代そのものが、きわめて女性がエネルギッシュに生きた時代だった。たとえば狂言などにしばしば<わわしい>女性たちが出てくる。男と同等の経済活動をやってるのは、何も富子だけではなかった。亭主に金貸して、それを返さないと訴えて、金を取り戻す話もある。武家社会においても女性の財産権はきちっと守られているし、夫婦別姓だし、ひょっとしたら現代よりも女性の主体性があった時代かもしれない。
そうすると、過去の物語として描きながら、近未来ドラマ的なテーマを据えることも可能だ。何よりもテレビドラマとして面白いのは、夫婦ドラマとして描くことが出来る。そこで、ストーリー展開については、日野富子と夫の足利義政の夫婦ドラマという視点で貫いてみたんです。富子の時代背景となる応仁の乱は、複雑怪奇な乱で、どっちが正義かどっちが悪か分からない。しかも、どっちが勝ってどっちが負けたのかも分からない。ヒーローも出てこない。とてもドラマになりにくい。これも、富子と義政の夫婦喧嘩の延長線上で摑まえると、きわめてすっきりと割り切れるんですね。そこを軸にしたストーリーを添えまして、それに『花の乱』というタイトルを乗っけて提出した。それを元に、プロデューサーやディレクター諸氏と、テーマ性やタッチの問題をさらに突っ込んで検討を重ねて、一応の合意が出来たところで、これでいこうということになりました。それがスタートです」
二人の富子を発想
――日野富子は創作意欲をそそる魅力があったわけですね。
「富子の個人的な魅力もさることながら、室町を中心にした町衆、つまり庶民の力が強くなっていく。流通経済の基礎が出来はじめてくる。そういう高度成長期の中で、一方で幽玄の世界、世阿弥、音阿弥などを中心にした能狂言、お茶、お花、作庭、それに遺明船が運んでくる明からの文化。絵画などにも大きな影響与えている。それから一休や蓮如に代表される仏教文学、その二つの要素が同居した社会、両極が共存している対比の世界ですね。光があるから影がある。強烈な光があるから漆黒の闇が生まれる。聖があるから俗がある。この世があるからあの世がある。そういう時代背景というのは、僕の作劇の中でも好みの、虚と実の狭間でさまざまなものを思考する――人間たちの存在の仕方、アイデンティティというようなものが一元的でなく捉えきれる世界である、ということに気づいたんです。
そうすると主人公である富子自身の中にも、たぶん両極が存在する。悪女といわれながら実はそうでない面もある。という延長戦上から、富子の中にある善なるものと悪なるもの。富子の中にある聖なるものと俗なるもの。そういう捉え方をしていきはじめたら、富子が僕の中で二つに分かれてしまったんです。つまり、二人の富子がイメージの中で出てきてしまったんですね。そこで、これは極めて大胆な仮説になるんだけれど、富子が二人いたらどうなのだろうかと、ふっと思ったんですね。それを思った瞬間に、ああこれで出来たかなと、ちょっと思ったんです。これが核かなと。つまり、単に史実をなぞるだけでなくて、逆に史実を利用し、史実を超えた物語性を構築していくという、歴史ドラマの作り方の本来の魅力にちょっとたどりついたかなという気がしました。
それで同時代の女たちを眺めてみると、森侍者という盲目の遊芸人がいる。歴史の上では一休宗純が七〇歳の時、その女に溺れた。『狂言集』では盲目のその女にメロメロに溺れこんでいく赤裸々な人間性をさらけだす、その対象の女性ですよね。非常に清らかな魂の澄んだ、この森侍者が実は富子だったというふうにしてみたらどうなるだろう。盲目なるがゆえに、日野家を追放になった本当の富子。今ある富子は替え玉の富子。ただの替え玉だと、あまりに歴史の冒涜になるから、日野家の血は引いていることにする。母親が盗賊に犯され、その胤を宿したとする。それゆえに里に預けられていた子が、本当の富子が盲目になったためにすり替えられて、富子として戻ってくる。この女性は盗賊の血も引いているから、わわしいエネルギーは、その鬼の血を引いたものだとすれば、公家の姫でありながら、そういう育ちを超越したあるわわしさ、今後富子が行動していく、枠を超えたエネルギーはそこからある必然性が出てくる。もう一人の聖なる富子は盲目の遊芸人として殉教者の道を歩む。この二人の富子という捉え方で、富子像も極めて明確になるし、この二人の富子を描いていくことで、室町という両極文化の時代の特徴が出ることになる。そういう発想は、一番最初の企画書では考えもしていなかったことです。そこに行き着いた時に、一つの物語として成立する。これで本当の室町の姿、室町ごころという言葉があるんですけど、その室町ごころを描き出すことが出来る」
義政という男の生き方
「富子をそういう設定にしてしまうと、義政という男の、女の愛し方の悲劇性も定まるところが出てくる。義政の根本にあるものは、浄土思想に裏付けられた彼岸願望。生まれながらに将軍として生まれ、自分が選んでもいない女性を代々のしきたりということだけの理由で日野家から富子を嫁さんとしてあてがわれる。そういう全て他人から与えられた人生を生きてきた男が望むことは、本当の自分探し――本当の自分は何を求め、自分らしい生き方は何なんだとということをたえず自問している。だから広い御所の中でも、本当の世界は“箱庭”にしかない。小さな箱庭を作って、善阿弥という庭師を相手に、そこで自分で行きたい世界を描いていくしかない。若い時には、将軍として世のため人のためがんばろうとした時期もあったけれども、組織の中でがんじがらめになって、どうあがいてみてもお飾りの将軍としてしか扱ってもらえない。しかも迎えた女性は自分よりも極めてバイタリティに溢れている。そういう義政の彼岸願望は、現実の妻の富子と格闘しながら、本当の彼の理想は森侍者という、嫁さんにはしなかった、もう一人の富子。そのもう一人の富子は義政にとって永久に手に入れることが出来ない。しかし本当は義政みたいな性格の男は、森侍者みたいな女と一緒になってこそ幸せな夫婦生活を送ることができただろうに、現実は極めてわわしい富子と関わっていく。
現実の女と夢の女との狭間に、立たされている男のロマンチシズムの悲劇。義政は将軍なので、逃げるに逃げられない。離婚したくても出来ない。夫婦喧嘩が絶えない。お金のことでも息子のことでも、喧嘩を繰り返す。ただ、偉かったのは、この両方が逃げなかった。とことん喧嘩をしつくして夫であることを全うしてしまった。そうすると、これはまだ僕の中でも分からないけどそこにも何がしかの愛が生まれるのではないか。常にプラトニックに存在している森侍者への観念的な夢の愛とは別に、泥まみれになりながらも、お互いに傷つきあいながら関わりをもつ女性との間に、でも逃げないで何年も積み重ねて、その二人に何か愛らしきものが芽生えるとすれば、それがこのドラマが求めていたものにもなるだろう。それが得られたら、もうこの話は終わっていい。そうするとこの夫婦のどちらかが死んだとき、義政というさまよえる魂の帰結、義政の魂が行き着いたところが、この話の終わりにもなるというふうな位置に据えているんです」
どこから始めるか
「じゃあ最初はどう始めるべきかが、次に考えることです。まず、歴史ドラマは編年体で書かれていくのが普通です。このドラマも、富子のおいたちから、二人の富子のとりかえばやから、始めなければならない。つまり生まれたところからやらなくてはならない。五、六歳で取り換えられるそれもやらなくてはならない。十五歳で興入れをする。義政と富子が結ばれて結婚していくという流れも追わないといけないとすると、やはり編年体でいかざるをえない。それでもいいんだけれど、一つの問題は、せっかく主人公に三田佳子、夫には市川團十郎という大看板をもってきたのに、この二人の登場がずっと後になってしまう。
三田さんと團十郎の年齢の問題もあります。歴史劇ですから相当のコスチュームプレイで二十代くらいまでは可能としても、十代は無理だろう。舞台とは違いますからね。大ざっぱに組んでいっても、十話ぐらいまでは若い時の話になるかもしれない。そこまであの二人が出ないというのもしんどい。そうすると回想形式にせざるを得ないけど、一人の人間が回想するといっても回想は、自分の主体的な記憶はせいぜい五、六歳ぐらいからしかない。この話では自分が生まれた時からやらなくてはならない。ちょっと困ったなと、資料を漁っているときに、参籠という言葉が目に止まった。当時の女性たちは、いろいろ思い悩んだ時に、お寺さんに参籠して何日間も飲まず食わずで、お籠もりをさせて、それは富子の記憶ではなく夢、夢として自分の生まれた時のことを夢見ればいいと。富子自身は、その夢のお告げは何なんだ、何を告げようとしているのか…富子の最初の問題意識にすればいい。
それならば、大人になった主人公たちも出せる。参籠から始めよう。じゃあどの時点で富子が参籠するか。歴史年表を追っ掛けていくと、必ずエポックがありますよね。あの事件、あの一言、義政夫婦の場合には、寛正五年に、義政が『もう将軍をやめようと思う』と言う瞬間があるんですね。その一言が、あらゆる混乱の原因を招いていく。夫の義政のその一言を富子が聞いた時。そこを出発にしようと。その一言によって、自分の進退を決めなきゃならない富子が、自らその答えを見出すためにお籠りをした。そのお籠りの答えとして、自分が生まれてからの夢を見る。第一話はそこから始めることにしました。
誇りをもてる仕事を
――オンエアが始まる前の作家としてのお気持ちは?
「歴史ドラマというのは、娯楽性と文化性、その両面を考えていく必要があると思うんですね。歴史ドラマという以上、そこには講談的な物語性の面白さを追求するのと同時に、歴史そのものが持ってる文化性。僕は、その両方の面から、今回はどうしてもある格調を失いたくなかったんです。面白くすること、それから分かりやすく見せることは、もちろん必要なんですけど、それがために歴史ドラマの持つ格調までが失われることは避けたいと思った。格調というのは、何もお高くとりすますことではなくて、人間の誇りなんですよね。誇りあるドラマを作る、それは作り手が誇り高くドラマを作れる。そういう場をまずシナリオが提供する。そのシナリオがスタッフにもキャストにも、格調高く仕事をしようという呼びかけ、まさに脚本の内容に関わっていくわけですね。そういう作り手のぎりぎりの誇りを支えてくれるのは、結局は視聴者なんです。
今のテレビドラマは、視聴者のレベルを相当低いところに置いている。ドラマというのはバーゲンセールじゃない。安売りをすれば、どんどん品物がさばけるというような、どこかの電機店の社長がやってるような、ああいう数字取りにドラマが走っている。大河ドラマまでがそこに流されていってしまうという、安売りで点数を稼ぐようなドラマづくりは、断固したくない。やっぱり歴史ドラマはその内容が持ってる娯楽性と同時に歴史の格調というもの、つまり、おおげさに言えば民族の誇りと言ってもいいとも思いますが、究極的には、個々の誇りにもつながっていくんですけど、その姿勢は貫きたい。今後どういう数字になっても。つまり、視聴率というものがどういうかたちになって現れようと。それが良かろうと悪かろうと、そういうことに左右されずに。演じる人も、NHKの作り手も、自分はあの時『花の乱』に関わったと、ずっと誇りとして持ち続けることの出来る脚本を書き続けたい。それが、脚本家に出来る唯一のことだと思うんです。
1994年6月号
第2回 歴史ドラマの人物設定
史実とフィクション
「歴史ドラマを書く作家が、必ず最初に自分の中で課題とするのは史実とフィクションの兼ね合いです。どこまでを史実通りにし、どこまでフィクションが許されるのか。そのバランスが、大河ドラマの場合一番大事なんです。その調合を間違えると、歴史ドラマにならない。史実だけを先行すると、殆ど『歴史への招待』みたいなものになりますし、フィクションを先行してしまうと、『時代劇』になってしまいます。大河ドラマを「新講談」たらしめているのは、そのバランスなんです。
たとえば、どんな人物を登場させるか。歴史上の人物だけではなかなか展開がしにくいので、当然、フィクション――歴史上には出なかった人物も登場させなきゃならないということがあります。室町は戦国時代と違って、まだ英雄名将がいないだけに、庶民の側にも名前の残ってる人が多い。『黄金の日々』は戦国時代の話でしたが、あの頃は侍以外は、殆ど歴史に名前が残ってない。にもかかわらず、納屋助左衛門という堺の一商人を主人公にした。史実でいうと、二、三行しか出てこない人物で、作品の全体のコンセプトとしては、自由都市堺の納屋衆、会合衆というものが主人公でした。その代表人物が助左衛門ということです。
そのように殆どフィクションの人物を主人公に置く場合には、逆にその人間にリアリティを持たせるために、周りを全部歴史上の人物で囲んでしまうというやり方をとりました。
『花の乱』の場合には、室町時代は天皇、将軍、五山の僧たちと同じくらいの比重で、京都の町衆が登場する。最下層とされていた河原者の中から善阿弥という庭師が出てきたり、世阿弥などの芸能者も活躍している。まだ、日本の歴史上の記録として階級差が偏向していない。それが室町の特徴だったのかもしれません。今と似てるところがあるんですね。つまり戦争があるとどうしても英雄英傑が中心になりますけど、平和な時代は平等に階級差を越えて歴史が書かれます。
今回に関しては、そのバランスを取るためにフィクションの人物を新たに登場させ、その人物を作るのに大変苦労したということは比較的少なかった。その代わり、登場してくる歴史上の人物の肉付け…その人物のこのドラマへの関わり方に、史実にはない振幅をもたせていくことに苦慮した。
一例を上げれば、一休宗純という人物、例の頓智で有名な一休さんなんですけど、この人物をどう『花の乱』の主要人物たちと関わらせるかという時に、一休の出生に関していくつかの説がある中に日野家と遠い親戚だという説があったんですね。であれば、『花の乱』の中心人物たちと関わりを持たせることが出来るということでその説を取る。つまり、史実的にはどっちが信憑性があるか、どっちが正しいかということよりも、どっちがドラマに関わりやすいかという方向で選択するわけです。
『花の乱』で一番、歴史の記録にない所での脚色は、日野富子が実は二人いたということです。しかも、もう一人の富子は森侍者という盲目の遊芸人であると。それが史実であるかの如く脚色をしていく設定です。
なんで、そこに僕がこだわったかと言いますと、『花の乱』のドラマの構造そのものが、いろんな面で、二極対立のドラマになるという特徴があって、その全体構想にぴったりとはまったということがありますね。応仁の乱そのものが東軍と西軍に分かれる。それがそのまま富子と義政の夫婦喧嘩の対立に結びついている。義政は生まれながらの将軍で、本当の自分は他にあるじゃないかという意識で、将軍職という自分の運命から逃れて、出家したいという願望が強くある。マイナス志向をもった理想主義者。妻である富子はもともとは日野富子ではないのに日野富子にさせられて、より将軍御台所であろうとするプラス志向を持った現実主義者。その対決でもある。室町時代を包含している仏教思想――地獄対極楽、生と死。天皇、将軍と河原者。そういう対極が富子の設定にまで広がっていくとすれば、一方の富子が将軍御台所として俗なるところにいれば、もう一人は聖なるところにいる。森侍者は世俗と全く対極する彼岸の場所にいる。という所にもう一人の富子は置きたい。
そういう対極のドラマで大きな意味を持つのは『橋』なんです。つまりこっちの世界とあっちの世界を結びつけていくのは橋しかない。中世の橋の意味というのは、この世とあの世、聖なるものと俗なるもの、光の世界と闇の世界を結びつけていく懸け橋という、この世でもあの世でもないそれを結びつける中間的な位置を持つ。それゆえに、魔が存在する。例えば、一条戻り橋などもそうですけど、様々な怪異現象は橋の上で起こるのは、そのせいなんですね。中世の人たちは橋というものにとても神秘的な特別の思いを昔からもちつづけている。
二人の富子を結びつける唯一の証拠品として、『火の橋』『水の橋』という二本の扉を設定しましたけど、二つ繋ぐと一つの橋が懸け渡ることになる。扉は橋の真ん中で割れて二本に分かれている。橋の絵も一方は都が炎に包まれている図、その端には橋が半分かかっている。その橋はどこへいってるのだろうと見ると、滝が流れる山里の村に繋がっている。それは都と地方を繋ぐ絵になる。二人の富子を繋ぐのも扉の中の橋だと。
そういうさまざまな所で、一元的でない世界が対決していく、時に共存していく。それが室町時代全体の特徴なんですね。他のどの時代にもない。だから、室町を描く時には、必ずその対極の世界を意識してやらないと、室町時代にならない。富子の内面にまでそれを浸透させたかったものですから、ぜひ森侍者を富子にしたいと」
一流の歴史監修者とは
「こういう史実とフィクションの兼ね合いで、話し合いをする時に、僕が対決するのは、監修をやって下さる歴史の先生方なんです。今回の場合には、横浜市立大学教授の今谷明先生と、國學院大學の二木謙一先生。両教授に歴史監修をお願いしてるわけですけど、そのお二人の先生との話し合いになるわけですね。歴史の先生方も監修を引き受ける以上、そのドラマが史実としておかしくないということを監修する義務があるわけです。ですから、そこまではやり過ぎだよとか、それは史実に則してますということでのみ、ドラマに関わってくる。これは脚本づくりの非常に重要なプレインの一角なんですね。
僕はまず、この設定は、先生方からの大きな抵抗があると思ったんです。森使者も一休宗純の研究者からすれば、一休に『狂雲集』という歴史に残る詩集をつくらせた鑑のような女性ですからね。この人物が実は日野富子だという話ですから、とんでもないことだと言われて当たり前かなと思っていた。当然、最初話した時にはエッ?ということになりまして、僕はドラマの必要性からいろいろ先生たちに説明をするわけですからが、先生方からすれば、その話が面白いか面白くないかはどうでもいいことなんです。それが史実としてあり得たか、あり得なかったかということが、基準なんですね。自分たちの名前をタイトルに出す以上は学者としての責任もあるわけですからね、そこは先生たちはシビアなんですよ。
それが、両先生ともある程度の驚きは禁じえなかったようですけど、断固それは許さないというところにまで至りませんでしたね。それまで言うなら仕方ないという苦笑で終った。僕は、その時に、彼らは一流の学者だと思いました。『黄金の日々』は桑田忠親先生という中世史の大学者にお願いした。僕は桑田先生の歴史ドラマへの関わり方を先に見てみましたんで、桑田先生的見方をする人かしない人かで、一流か三流か自分の中で見分けてたんですけどね。
一流の歴史学者というのは、今残ってる記憶を究極までつきつめます。われわれから見ると、無尽蔵の知識を持ってる人に見えるんですが、トコトンつきつめてる専門家にとっては、記憶として残ってるものはたったこれだけなのか、もっといろいろある筈だという意識が強いんですね。知っていれば、いるほど。だから、彼らがドラマを見る基準は、記録として残っているものはたったこれだけなのか、もっといろいろある筈だという意識が強いんですね。知っていれば、いるほど。だから、彼らがドラマを見る基準は、記録として残っているもの以外は歴史になかったことだとは決して見ない。記録上実証できない事柄は、全部、あり得たことかもしれないこととして、認めざるをえない謙虚さも同時に持ってるんです。それが絶対なかったんだと彼らが言う時には、きちっとした記録からの根拠があって、おっしゃるんですね。どの時代までは薙刀で、この時代は槍があったとかなかったとか、そういうのを彼らが指摘なさるのは記録があるからなんです。
こっちの想像力は、記録を超えたフィクションとして、当時のことをいろいろ想像しますね。学者の側からすれば、いやそれはなかったという否定できる材料がない限りは、認めざるをえないという立場を取られるんですね。なるほどあったかも知れない。日野富子が実は参籠の時、盗賊に犯されて胤は盗賊の胤だと、彼らがそれを否定しないのは、つまり絶対になかったという記録がないから、認めざるを得ないんですね。森侍者についてもその出生が全く記録として残ってない。何処で生まれ、どんな親で、どうして盲目になって、七十歳の一休と知り合ったか、という記録は全然ない。森侍者が三十そこそこの頃に一休と出会った時から森侍者の記録は始まってるんです・それ以前は、全く記録にない。想像の分野になる。その想像の分野で作家が創造したものについては、それはおかしいよという言葉は一流の学者からは出ないんですね。つまり、一流の学者ほど、より誰よりも記録を知ってるだけに、その限界も知っていて、そこから想像できるキャパシティの許容量が広いんですね。これは、ちょっとした郷土史家や素人学者、歴史愛好家が趣味的に述べるレベルからいうと、自分が知らないこと自分の知識の範囲を越えることが出てくると、断固、まるで自分のプライドを傷つけられたがごとく、得意がって否定するわけですよ。『そんなことあり得るわけがない』みたいなこと言ってくる。固定観念というやつですね。それにこだわる人は、三流ですね。それは僕がいろんな歴史学者たちと関わってきた、端的な違いです。
大河ドラマの監修の先生選ぶ時に、とにかく一流を選んで下さい一流ほど分かってくれる筈だ、と桑田忠親さんの例なども言って、そうしないと、二流三流の学者は必ず、自分の知識の枠内から出ようとしない。案の定、今谷教授も二木教授も一流なんですよね。非常に“あったかもしれない”という許容量が広い。その代わり、どんな小さい言葉の一行でも、完全にそれは間違いというものに関しては、断固許さない。それがあります。
1994年6月号
第3回 資料とシナリオハンティング
周辺人物の設定
「室町時代というのは歴史的にも奥が深くて、どこまで行っても知り尽くすということがない。底なし沼のような時代なんですね。ところが、その割には人物像が個人として浮かび上がってこない。行政方の記録としては、細川勝元と山名宗全が対立した理由とか、そういうものは図式としては辛うじて分かっているんですけど、もう一歩突っ込んだ人物像、それぞれが抱えていた内面の葛藤というようなものに関しては、分からない。戦国になると、様々な記録…それこそ『太閤記』とか『信長記』とか本人の自筆手紙、言行録というふうに残りますけど、室町時代の武将に関しては殆どないですね。細川勝元に関しては、鯉の料理で、その鯉が一体どこの川で捕られた鯉かということを看破したとか、山名宗全に関しては、公家が、それは先例があるのどうのとあまり先例ばかり挙げるものだから、大事なのは前にあったかなかったかじゃなくて、今、この時にどう判断するかが大事なんだと。“時こそ大事”と言って、先例ばかり言うやつを退けたという記録とか…その程度なんですね。
フィクションを作る側から言えば、逆に資料が多すぎてそれにがんじがらめになるのも困る。その人物像をより豊かにふくらませようとすれば、象徴的なことが一つか二つあればそれで充分ということがありますからね。『花の乱』の人物設定に関しては、末端までそれほど多くの虚構の人物を設定する必要もなく、歴史に記録されてる人物だけで、より多くの肉付けをしていく作業で良かった。
『花の乱』は応仁の乱が大イベントなんですが、その次に、都(みやこ)対地方の戦いになる。それが群雄割拠の戦国時代の前哨戦にもなる。地方の国人諸大名が領地争いを始める。というより山城の国一揆で言えば、国人を中心にして百姓たちが、一種の自治国を作って、中央政権政治に対して反旗を翻した。地方自治国の独立運動が起こってくる。『花の乱』では、山城の国の椿の庄というのを設定しまして、これを山城の国一揆の抵抗運動の象徴にしようと。そのリーダーに伊吹三郎という人物を設定した。この人物を、当時起こった様々な国一揆の代表者にした。この人物こそ、かつて富子が椿の庄に五歳まで預けられて、兄妹として育った富子より六歳上の“兄”の伊吹三郎なんです。これが、役所広司が演ずる人物として登場してくる。幼い時は兄妹として育って、もし富子が都に連れ去られて御台所になっていなければ、富子は、この伊吹三郎の妻になっていたかも知れない。この男と都側の中心人物となった富子が、対決をしていくという設定に広がっていくんですけどね。伊吹三郎というのは実は十人くらいの人間を一緒にしたフィクションの人間なんです。当時実在した何十人かの名もなき国人たちの象徴としての存在なんで、完全なフィクションとも言いがたい。そういう人物が時々大河ドラマには出てくるんですね。特に庶民の側にはね」
集中講義を受ける
「一応そういうふうなことを考えながら、様々な人物設定をしていきつつ、果たしてそういう話が歴史に乗っかっていけるかどうか、ということを計るために、僕らも、もうちょっと詳しく歴史を知らなきゃいけませんね。そのために、数日間、今谷明先生に集中特別講義を都内のホテルに籠もって受けたんです。『大日本資料』第八巻をテキストにして、『大乗院寺社雑事記』などをもとに、富子が死ぬまでの室町の歴史を。これはあくびが出るくらい退屈な授業でした(笑)。
というのは、いくら僕が資料を集めても、漢文の記録しかないものですから、学者の手を借りないと何が書かれているのかチンプンカンプンなんですね。漢文の解読を何日もしてもらう。高校時代の漢文の授業を想像してもらえば分かりますけどね(笑)。しかし、これはやらなきゃいけないんですね。そういう基礎的なところをやって初めて、同時にのびのびしたフィクションも安心して出来るわけで、知らないから想像力が勝手にふくらんじゃうというんじゃ情けないですからね。ある程度は分かった上で、こっちも嘘ばなしを作っていくんだという裏づけが必要なんで。退屈だったけれども、必要なこととして、そういうことに、随分時間をさいた。
昔は僕も自分の想像力だけに頼って、取材活動みたいなことをないがしろにしがちだったんですけど、やっぱり想像力の糧は史実、現実に何が起こったかということの正確な認識からスタートしなければいけない。より大胆な想像力を発揮するには、より正確な史実を把握していくことが必要だということは、長いもの(長時間のドラマ)を扱うとよく分かってくるんですね。それをいい加減にしていくと、早晩いきづまってしまう。
七百万円の資料を買う
「話が多少前後しますが、資料のことでお話しておきます。
大河ドラマの作家には、さまざまな資料が必要になってくるんですが、行きづまったら必ずそれを見るというバイブルのような資料が必要なんですね。『黄金の日々』の時は、ルイス・フロイスの『日本史』でした。『山河燃ゆ』の時には、原作がありましたけど、中身は殆どフィクションでしたので、もとになったのは『東京裁判』の記録です。それが僕にとっての本当の原作でした。同様に今回も基本的なところでの座右の書になるものを探しました。何がいったい中心の資料にしたらいいのか、相当悩みましてね。ないものですから。二日くらいディレクターの一人の小林武さんと二人で神田の古本屋を歩きまして、やっと行き当ったのが『大日本資料』だったんです。ところが、全三百巻くらい。そのうち室町時代に必要なのは十冊ほど。室町編だけ売ってくれと言いましたら、バラ売りはしないというんですね。三百巻全部買ってくれるなら譲ってもいいというんです。これを全部個人で揃えているのは、司馬遼太郎さんとか海音寺潮五郎さんとかのクラスの作家。だからそうそう簡単に譲れるものじゃないないんだというようなことを言われて、僕は悩みましてね。でもどうしてもバイブルが必要なんで、この際、清水の舞台から飛び降りた気持で買おうと、値段聞いたら七百万っていうんです。アチャーと思ったんですけどね(笑)。大河ドラマをなんのためにやったといったら、『大日本史料』買うためにやったと同じぐらいの額だなと思ったですけど、『ヨシ、いくぞ!』という心意気って大事ですからね。女房に内緒で貯金下ろして買っちゃった。七百万と引き換えに三百巻がうちへ来た時には、女房は殆ど泣いてましたけどね。この不景気の時にッて。(笑)。でも、そこで気持が少し落ち着くってあるんですね。それが非常に大事なとこなんです。あとは『応仁記』を見つけ出した時ですかね。ホッとしたのは。
シナリオ・ハンティングの目的
集中講義が終わったあとに、いよいよシナリオハンティングということになります。その時のメンバーというのは、二人のチーフ・プロデューサーとディレクター三人に僕を入れて六人。
日野富子、義政、応仁の乱、室町文化の遺跡を数日にかけて見てまわるわけなんですけど、シナリオハンティングの目的というのは、ドラマの舞台となるところを見学してまわる以上に、六人のメインスタッフの旅先でのブレイン・ストーミングが、実は一番大事なことになってきます。
宿屋で夕食を囲みながら、どういう方法でいくか、視聴率も取りたい、文化性、歴史性もないがしろにしたくない、格調も失いたくない。こうありたい大河ドラマの理想像を、ワイワイ話合う。興が乗ると朝まで、議論しあうということもある。
そこで僕らが、行き着いた『花の乱』の方向は、「芝居好きを満足させるドラマ」をやろうということでした。この方向性が大事なんですね。仮に、視聴率取りに走ろうと決めたら、キャスティングからその方向に走ります。歴史性を大事にしようとなると、話の全体のつくりから、変わってきます。それぞれ、一長一短はあるし、なかなかまとまる意見が出てこない。そういう中で、六人がやっと一致したのは、「芝居好きのためのドラマ」を作ろうということでした。
じゃあほんとに芝居好きが日本の人口の何割くらいいるか分からないけど、言ってみれば、身銭払って、新派とか歌舞伎とか新劇とか、商業演劇を見に行きたい、映画館に銭を払ってでも好きな映画を見に行きたい客たちを、テレビに呼びもどしたい。テレビの画面に、晩飯食いながらではなくてクギづけにして、このテレビドラマにだったら銭払ってもいいと思うくらいの、そういう満足度を与えたい。あとになって、それが高級過ぎるとか、筋が難しいとかいう声が上がりましたけど、その表現はわれわれの側からすると当たってないんですね。文句言いたい人も、むずかしいとか言わずに、「ドラマ好きのために偏向している」と批判してくれれば、頷ける面もあるんですけどね。確かに、危惧もしたんですから。テレビ観る人がみんなが芝居好きとは限りませんからね。
身銭払って芝居や演劇を見る人は意外と少数かもしれない。大丈夫だろうかと、誰かが言うと、いや大丈夫だと。やっぱりきちっといいものを作ってれば、客はだんだん増えてくるはずだと。大河ドラマは視聴率が悪いと」すぐ何だかんだとマスコミに叩かれるけど、じゃあなりふりかまわず、大安売りでバーゲンセールやれば一時的には客は呼べるかもわからないけども、安けり買うって客ばかり相手にしていていいのか。そのために大河がつちかってきた文化性とか、NHKでしか作れないドラマの価値というような一番大事なものを喪失してしまう。なによりも作り手がその仕事に誇りを持てなくなるのは最悪だと。
よし!ここは面白いドラマを作ってれば、客は増えていくと信じていこうと、その時に決まったわけですね」
キャスティングとドラマの方向性
「キャスティングもそういう時に、皆でイメージ・キャストを話合うんです。市川團十郎はあまりテレビに出てない、三田佳子と團十郎で富子と義政の芝居もいいだろう。京マチ子の芝居も、おすべらかしで室町あたりの芝居をやらせると、右に出る役者はいないんじゃないか、山名宗全は錦之介の風格で押し出してもらいたい、京マチ子と錦之介の芝居なんか映画でもみられなかった。狂言の若手の野村萬斎もいい、九代目幸四郎の娘で踊りの名手の松たか子、テレビにはまだ出ていないけど、この子を引っ張りだそう、など、芝居談義になっていく。つまり、芝居好きに見せようという方向で固まると、キャスティングもその方向で決まっていく。
そんな中、一方では、個々が自分の人生観とか、自分のドラマへの関わり方を吐露するようになる。例えば、黛りんたろうは、自分の幼年期にこんな体験をしたと言うわけです。――自分がまだ赤ん坊の頃、自分のうちの女中さんが、私生児を生んだ。出産が突然だったんで、僕の母親は赤ん坊を新聞紙に包んで、座敷に寝かせた。その襖一枚隔てた隣の部屋には、綿入れ布団におぼっちゃまの僕が寝かされていました。その話を後に、母親に聞かされたときに、僕はその新聞紙にくるまれてた私生児がいつか自分に復讐にくるのではないか、という怯えをずっと抱きつづけていました。新聞紙に包まれた隣間の私生児は、ほとんど自分の一部になってしまって、その一部が自分が演出するときの、ものをつくるときの発想の原点になってる。それは自分の永久の怯えでもある。しかし、その怯えこそ自分のあこがれでもある。いうような話を酒を飲みながらする。
僕のなかで、ますます二人の富子、というのも悪くないなと。偽物と本物の富子の対立は、りんたろうの怯えとテーマを一にする。そういう雑談の中から、極めて基本的な設定の核になるようなものが生まれてきたり、するわけですね。シナリオハンティングの目的の一番大事なところは、そういうところで、四、五日の京都の旅行から帰るときには、この大河ドラマで一番大事な最初の出発点の、方向性と、何に向かって九ヵ月間のドラマを作っていくかという、その方向性が個々バラバラではなくて、そこでメインスタッフが一致する。つまり共通の土俵が生まれてくる。決して作家が机上で一人で、あれこれ考えてやるわけではないですね。僕の中でも、シナリオハンティングが終わった時に、明快なドラマツルギーが生まれてくる。その時にはイメージキャストの顔まで浮かんでくる。
テレビドラマづくりというのは、制作も演出も脚本も具体化する程に分業になりますので、それだけのスタッフが一堂に会して話し合うって意外と少ないんです。個々ばらばらにはたえず会うんですが。メインディレクターの村上佑二を除けば、僕にとっても初めて関わり合うスタッフですので、個々のディレクターたちの思いとかが分かるわけですね。その時に、今まで自分がやってきた作り方のノウハウをお互いに押し付けあうのはよくない。出来るだけ、白紙で臨む。それぞれ作家も制作も演出もみんな今まで自分が関わってきた仕事の仕方がみんな違うんです。その連中が集まって新しい仕事をするわけですから、お互いの理解を深める意味でも大事なプロセスなんですね、シナリオハンティングというのは。
その時に、例えば「芝居好きのために作る」という方向だけでもガチッと出来ると、どんなに実力があっても一般には知られてない役者を呼んだ時でも、呼んだ役者さんに対してこっちが自信が持てるわけです。呼んだ理由がきちっとしてますから。誰それの引きだすとか、誰々一家の役者だからというようなキャスティングではないですからね。その番組がどんなに不振をかこっても、いろいろ文句を外野から言われてもそういうことで内部がガタガタするってことはない。一つの信念で貫いてる。そういうメインスタッフの信念と自信というものが、現場の隅々にまで浸透して情熱を駆り立ててさらにその作品の密度を濃いものにしていく。
そうすると、やっぱり反応というのは正直で、芝居好きな人たち、銭払ってもみたいという人たちはわれわれが想像していた以上に少ないんですけど、それでも見た人たちからの反応の葉書手紙の量はかつてないほど多い。見てくれてる人たちは相当に好きで見てくれてる。その葉書や手紙こそ、テレビにおける木戸銭だと。われわれの狙いは間違ってなかったんだ、このまま突っ走ろうということになっていくんですね。
1994年9月号
第4回 二つの悩みとスタッフ・俳優の熱意
台本担当の若いADたちに感謝
「(ドラマづくりの方向が決まって)いよいよ、シナリオを書き出します。大河ドラマの場合、(僕だけなのか、あるいは皆さんそうなのか、分かりませんけど)必ず台本担当者というのを決めてもらうんです。言ってみれば、助手的な役目をしてもらう人です。
大河ドラマは今度で三度目ですけど、『黄金の日々』の時はデスクをやってた中里(毅)さんに、その役目をやってもらった。毎日のように家に来て、ハコづくりまで手伝ってもらって、随分助かりました。『山河燃ゆ』の時は、やっぱりデスクの山本壮太さん。ところが、『山河燃ゆ』はアメリカでのロケがあったりして、デスクと台本担当との両立がなかなか難しい。負担が大きいので、台本担当者を外部から雇ってもらって、その人を秘書的な役目で付けてもらって、やったんですけど、これはうまく行きませんでした。外部の人というのは、全体の責任感も薄弱になるし、現場の情報が全く伝わってこない。なによりも、ドラマのストーリーに即した資料をキチッと揃えるということが、難しい。
ドラマの資料というのは二段階ありまして、一つは書きだす前の資料ですね。それから実際に書き出してから、細かい資料がいっぱい必要になってくる。その資料集めは、今の今、必要なわけですから、非常に敏速にやってもらわなくちゃならない。そのへんの機動力は、ドラマが分かってないとこっちが必要であるものに付いてこれないんですね。もたもたしてると、僕が調べたほうが速い、ということになる。
今度の『花の乱』では、どうしようかということになって、プロデューサーの木田さんと相談をした。方法は二つあったんですね、デスクかディレクターの一人になってもらう。あるいは、『山河燃ゆ』でやったように外部から雇う。ところが、『花の乱』は大河として初めて室町時代の世界なんで、デスクとかディレクターの仕事が多すぎて、台本づくりに付き合う時間がなかなかない。そこで、ADの谷口さん、篠原さん、中田さん、の三人でやってもらうことになった。三人ともまだ駆け出して、もちろん、台本づくりなんてやったことがない。NHKとしてもADクラスの人が、台本づくりにタッチするというのは前例がなかったらしい。ただ、僕が彼らでもいいなと思ったのは、谷口君や篠原君が、僕が脚本(ほん)を書き出して出来あがると、感想文を送ってくれてたんですよ。その感想文がとても素晴らしかった。これだけ『花の乱』を愛して、ドラマを分かってくれてる人であれば、若手でもかまわないと。
これが、台本のスピード・アップに貢献している。彼らはこれから演出家になろうという人たちです。運が良ければ、『花の乱』をやってる間に演出する機会があるかもしれないけど、ないかもしれない。しかし、『花の乱』の世界に関心が強い。こういう人たちに、脚本づくりに参加してもらう。すると、事前の打合せでも、ちゃんといろんな資料調べてきてくれるし、実際脚本を書き出してからでも、すぐ調べてくれる。
たとえば、将軍義政のことを『御所様』と言ってるんですが、ある日、息子が将軍になりますね。すると、義政を周りの人たちは何て呼ぶのだろうか、と思うわけですね。そこで僕が『退職後の義政は何と呼べばいいのか』とFAXを送ると、彼らは、時代考証の先生(今谷明、二木謙一、表章の各氏)を電話で捜しまくる。中世史の一流の学者たちですから、なかなか掴まらない。ようやく摑まえて、『大御所様と言えばいい』と。そういう細ごましたことをやってくれる。
それで、書きおわると、すぐ感想文をくれる。これが、励みになるんです。彼らが捉らまえてる『花の乱』の世界、彼らがこのドラマの中で興味を持った部分が、どこにあるかが、こっちにもよく伝わってくる。彼らはADですから、現場のこともよく分かってる。セット関係のこと役者関係のこと。どんどん正確な情報入れてくれるし、ディレクターたちにも殆ど会う機会ないんですけど、その辺のコミュニケーションもちゃんと図ってくれて、ディレクターたちの気持も代弁してくれる。若いですから、労力を惜しみませんし。まず、この若い人たちに台本担当になってもらったことが非常に良かった」
台本が長すぎる?
「脚本執筆が、どういうサイクルかというと、放送は一週間に一話流れるわけですから。こっちも一週間に一本は書いていかなくてはならない。木曜日くらいに、まず打合せをします。この回はどうするか、流れはだいたい決まってるんですが、その回のストーリーづくりみたいなものですね。それは、わが家でプロデューサーの木田さんと、若手の台本担当。時間があれば、その回のディレクター。ストーリーだけではなく、けっこう細かいコンストラクションまで作ってしまう。そこで、大筋が彼らは分かりますね。そのことで準備できるものは、その段階からするわけです。僕のほうはその日から書き出して、木、金、土、日、月曜日か火曜日にあげて、渡すわけです。まず、それが準備稿になって出来てくる。その準備稿をもとに、台本担当者が、時代考証の三人の先生に見てもらって、言葉の間違いはないか、歴史上の飛躍の限度はその辺でいいかどうか、時代考証のチャックをしてもらう。それがこっちに返されて、直していく。それで決定稿になる。
『花の乱』が準備稿から決定稿になるときに僕とスタッフが抱えている課題は収録した時間が台本より伸びてしまうということなんです。大河ドラマは四十五分ですけど、僕もプロですから、四十五分ならだいたいこれくらい入るだろうという目安で書きます。『花の乱』の場合、その常識的目安をはるかに越えちゃうんですね。
原因のひとつは、芝居のテンポなんです。それは、今回の『花の乱』の狙いが、役者の芝居を見せよう、物語性を高くして情感で押していこうということがあるものだから、各役者さんたちもたっぷり演る。こっちが想像している以上にたっぷり、それでどんどん延びていく。普通ですと四十五分ですから、おおざっぱに言っても、四百字詰めだと、一分一枚と計算すれば、四十五枚から五十枚。ところが、いざ撮って編集でつないでみると、毎回長い。これを編集でカットしなくちゃならない。情感の部分はカットしにくい。かといって、歴史ドラマですから、普通にしゃべってることでも、言ってみれば歴史ドラマの情感を相当に入れこんでいる。そこを切ると歴史が分からなくなっていく。それを切っていかなくちゃならないということだった。
どこをカットするのかは、それぞれ皆個性的なディレクターたちだから、人によって興味の置き方が同じ回でも違いますので、そこは演出の主体にまかせているんですが、僕の気持としては、台詞を間引きされるよりも、シーンごと落としてもらったほうがいい。というのは、大河ドラマというのは、ホームドラマのように、一つの話を四十五分で、起承転結をつけていくというだけでは成り立たない。つまり、いくつものシークエンス、いろんな状況が、てんでバラバラにありますんで、たとえば主人公を太陽だとすれば、その惑星をきちっと描いていかないと一つの宇宙にならない。
これは、僕の大河ドラマの考え方なんですけど、ワン・シーンにもかならず、起承転結をつける。小さいドラマの積み重ね、小さい起承転結の積み重ねが、四十五分の大きな起承転結につながっていく。それをやってるんですね。だから、どのシーンにも必ず起承転結を、二人だけのやりとりでも必ず起承転結がある。そういうやり方をしてますので、一つのシーンのどこかの台詞を抜くと、そのシーンの起承転結が崩れる。それをチョコチョコやられると、全体が起承転結を失いますから、犠牲にするなら、どこかをばっさり犠牲にして、他を傷つけないということを希望してるんですけどね。理想は、どこも切られないで、全部放送されるのが一番いいんですけどね(笑)。今日(七月二十日)の時点で、十六話まで放送してますけど、その全編に渡ってあるんですね。いまだかって、脚本通りに全部放送されたことがない(笑)。
だったら、こっちがページ数を減らしていくしかない。その発想の転換を今、強いられてるところなんです。普通四十五分といえば民放では一時間番組です。われわれのドラマをつくる許容量の目安というのは、一時間つまり六十分ドラマか三十分ドラマなんです。
六十分ドラマと三十分ドラマでは、コンストラクションの組み方が全然違うんですよ。四十五分ドラマのコンストラクションの組み方って聞いたことがない。だから、たいていは、六十分ドラマの発想をして、それをいかに四十五分ドラマに縮めていくかという二段階の作業をしていく。『花の乱』でも、六十分ドラマの発想をしてそれを四十五ドラマに縮めていく作業をしたんですけど、この発想じゃ間に合わなくなってきたんですね。
どんなに枚数を縮めても、シークエンスが多いものですから、やらなければならないことが、いっぱいあるわけですね。それをカットすると全体の起承転結が崩れていくんです。それで、ここ二、三回やってるのは、最初から三十分ドラマの発想をする。三十分ドラマの発想で例えれば四十枚くらいのものにするとなると、かなり余裕が出てくる。今までは一つの鍋に六十分ぶんの中身を入れてグツグツ煮て、吹きこぼれていた状態を、中身を少なくして吹きこぼれを少なくする。多少、中身の具は減りますけど大根の味とか人参の味わえる。ようなやり方に切り換えたんですね。
もう一つ頭を抱えている問題は、登場人物一人の人間が持ってる名前の多さなんです。たとえば、足利義視(よしみ)という人物、これは最初の義尋(ぎじん)という禅僧です。これが還俗して足利義視になります。ところが、この義視はテロップには義視と出すんですが、劇中で『よしみ』と呼び捨てに出来るのは将軍しかいない。他の人は『今出川様(いまでがわさま)』と呼ぶ。当時は住んでる場所の通称で呼ばれるんですね。義政だと『室町殿』と呼ばれたり、『東山殿』と呼ばれたり。義視も、公の場では、官位で『左馬ノ頭(さまのかみ)殿』と。これをなんとか一つの名前で台本上統一しようと思うと、今度は学者の先生からクレームがつくんですよ。いや、ここの身分の者なら左馬ノ頭様と呼ばなくてはならない。殿では駄目で様でなくてはいけない。一人で三つくらいの名前が錯綜する。細川勝元は、劇中では右京太夫(うきょうだいふ)と言ってます。テレビで、右京太夫というのは細川勝元のことなんだと分からせるテクニックを考えなきゃならない。こっちも、それは相当念頭に入れて書くんですが、まだ分かりにくいって言われますね」
台詞で役者の力量が試される
「今回、僕の脚本が速いと、みんな首を傾げてる。いろいろ理由はあるんですけど、FAXと宅急便のおかげで、ずいぶん時間を節約出来るようになった、ということも一つにはあります。
FAXで思いだしましたけど、主演の三田さんとは、電話で話したり会ったりすることは殆どないんですけど、FAXの応酬はしょっちゅうやってるんです。三田さんが、『花の乱』の主演者としての自覚と、日野富子という人物に乗ってくれてることが、現場の雰囲気を非常に良くしてくれるか、ということは、大事なことだし、全体の雰囲気を左右しますね。
ついこないだも、撮影もちょうど真ん中くらいにきて、登場人物も入れ替わったりするということもあって、メインスタッフと主演級の人たちと隅田川で舟遊びしましてね。屋形舟借りきって繰り出してパーティやった。その後に、みんなで近くのウォーター・フロントの三田さんのマンションへ行って、明け方まで飲んだり話したり、團十郎、奥田瑛二、佐野史郎…殆どみんな来ましたけど。そこで皆が、僕の長い台詞をどんなに苦心惨憺して本番までに覚えてくるか、ということを言ってましたけどね。
草刈正雄などは、あんまり台詞の量が多くて、それを詰め込んでいるうちにとうとう頭痛がして、病院に行ったそうです。診断は、台詞の覚え過ぎと言われたそうです(笑)。つまり、そういう結構過酷な台詞まわしを役者たちに強いてるんですね。日常会話じゃないですから。さまざまな歴史の情報と、しかも難しい言い回しで役をこなさなきゃならない。現代語のように、ちょっと言い間違えても、ニュアンスが伝われば、まあいいかというようなわけにはいかないですね。テニヲハからきちっと覚えないと成り立たない。もちろんアドリブ入れたくても言えない。ルー大柴なんかカチコチになってやってるでしょう?(笑)。
しかも、役者たちがさらに緊張するのは、言ってみれば全部が、そういう芝居ぜりふですから、うまい下手がわかってしまう。ごまかしがきかないんですよ。どれだけの力量をもった役者かある程度長い台詞をしゃべらせると、一目瞭然なんです。役者さんたちも、そのことがよく分かってますから、なおさら、緊張してやる。
僕は、自分でしゃべりながら台詞を書くんですよ。素人の僕が、どれだけ気持よくしゃべれるか、句読点一つ間違えても、なんだかごちゃごちゃした台詞になりますから。どんなに長い台詞でも、役者さんにとって、入りやすい台詞と入りにくい台詞があるんです。どれだけ、役者として入りやすい台詞として書くかということは、こっちの義務ですから、考慮して書く。
役者って大したもんだと思うのは、僕の中では、この程度の感情でしゃべってもらえば、成り立つという思いがあるんですけど、三田さんや團十郎クラスになりますと、こっちの思いははるかに越えた情感をその台詞に入れるんですね。このシーンがこんなに劇的な緊張溢れるシーンになったのかと再認識するということは、しばしばありますね。その逆ももちろんあるわけです。こんなに気持いい台詞で書いたのに、なんだこのヘタクソは、それでも役者か、と思うことも正直ありますけどね(笑)。
『花の乱』の現場が、いまとてもうまく行ってるというのは、そういう苦労を乗り越えながら、役者さんたちが乗ってくれてるということと、現場の若い人たちが、この世界をとても愛してくれている。僕等の知らないところで、若い者同士、スタッフや若い役者さんたちが仕事が終わっても飲みに行って『花の乱』の世界のことを、カンカンガクガク議論してる。本当に『花の乱』を体で支えてる人たちが、情熱をこめてやってくれてるということが、実は、全体をうまく作っている。それを支えているのは、一口で言えば、いまだかつてやったことのない新しい大河をやってるという緊張感なんですね。テーマ性も単なる勧善懲悪ではない、かなり現代の人間にも通じるテーマで、毎回やってる。エンターテインメントとしても、一見古臭く見えながら、実はきわどいことをやってる。そのことへの誇りとか喜び、それがなんとなく全員に以心伝心で伝わっていってる。誰かが突出して、他がだらだらとついていってるというような、ことではない。
僕が作家の立場で『花の乱』に関わるときに、志した思いと、一つになった。みんなが、やっぱりやって良かったんだ、失敗も成功も含めてやらなければならなかったんだ、ということを、現場の若いスタッフたちが確認しあっている。僕がやらなければならないと思ってたことが、そのまま、伝わっていったという喜びに、今浸っています」
1994年12月号
第5回 登場人物の交替から 最終回を書き上げるまで(最終回)
登場人物をいつ殺すか
――二十五回あたりから主要な人物が次々と死んでいきましたが、その展開の意図は?
「歴史ドラマの宿命として、主人公を軸に周りの主要人物がどんどん流れていく、変わっていく、この変わり目を計算していかなくてはならないんです。山名宗全がいつ死ぬか、細川勝元は、日野勝光は、一休和尚はどう死なすか、森侍者というもう一人の富子にどんな死に方をさせるか、等々を年表を見ながら考える。(ドラマの)中身は歴史通りにいかない面が多いんですけど、実在した人間の生まれた時と死ぬ時は変えないのが原則です。山名宗全が人気があるから、もうちょっと延ばそうかということは出来ない。
その辺のことは、当然役者さんのスケジュールがらみのこともあるんです。“ここまでです”と役者さんに伝えておくわけです。役者さんの側からも要望もある。奥田瑛二は次の熊井(啓)さんの映画に入らないといけない、野村萬斎は一年間イギリスに留学に行かなくてはならない。そういうスケジュールの相談とこっちの話の進み具合を見ながら、二十話くらいを書きおえたときに、その役の最終結論を出すわけです。そこを一旦決めてしまったら、絶対に動かせない。役者さんに伝達してしまえば、こっちの話の都合でもうちょっと延ばすというわけにはいかなくなる。そういう所で、宗全を殺し勝元を殺し、『花の御所炎上』で勝光を殺すわけですけど、芝居で言えばそこで第一幕が降りる。ある種の結末がそのあたりにかかるんですね。話全体も、それまでは応仁の乱を中心に描いていた話が、その主要人物たちが消え去るのと同時に、話の展開もまた新たになっていかなくてはならない。
ただ、これだけ急激に主要な人物が消えてしまうと、作者自身の中に、ポカッポカッと空洞が出来るんです。もちろん、やらなくちゃいけないことは、次々に出てくる。ドラマ全体も世代交代で若いグループがどんどん出てくる。同時に、それまで抑えこんでいた主要人物、例えば役所広司の演ってる伊吹三郎という存在は、山城の国一揆の主要人物として待機させてあるわけですね。それまでにも出てくるんですけど、応仁の乱が終わった後の、山城の国一揆に突入していく時の伏線として張ってきた。そういう人たちを迎えて、新たに話を展開していくという緊張感も生じると同時に、消え去った人たちへの惜別の情というのも、同時に感じるんですね。
応仁の乱が終わった後は、展開としては山城の国一揆へ向かっていく。つまり、対立図が富子対山城の国、富子対伊吹三郎、幕府対土一揆あるいは惣国。国入百姓たちによる自治の、つまり自分たちで治めていく国造りというのが、この時期に一つの運動として、起こってくる。これはいってみれば、幕府の世話にならないという運動です。地方自治体がもう国には税金を納めない、長崎県なら長崎県で独立国作ってやるからみたいなもんですね。幕府にとっては由々しきことで富子はこれを弾圧しなくてはならない。弾圧する相手は、兄として育った人という縮図が生じてくる。
<
富子の苦悩、悪女の由来
一方で富子の息子の義尚が将軍になる。富子は応仁の乱を起こして、対立してまでも、将軍の座に据えた息子なんだけれども今度はその息子と対立してしまうんです。ある時などは、義政の側室と恋愛関係に陥ったりして、親父と三角関係になったり、もとどり切って家出しようとしたり、最後はとうとう近江の国の六角(高頼)攻めの指揮を自らとって、三代足利義満以来将軍自らが出陣をするというようなこともする。この出陣もまた、政治に非常にふがいなかった父親への反発でもあり、また自分が将軍になっても、なんだかんだと口を挟んでくる母親への抵抗でもある。自我に目覚めて、母親から独立して出陣してしまう。その出陣先で病死してしまうんですね。
管領細川勝元の息子の政元も奇行はなはだしく一種狂人で、修験道に凝ったりして、飛行術なども試みたり、大層変わった、しかし極めて独裁的な政治家なんですね。富子はこれにも手こずるわけです。
それ以前の話で言えば、応仁の乱が終わって京都の半分が焼け野原になった。富子は京都の町の建て直しをやらなくてはならない。家庭はガタガタしてて、義政は家出して山の中に籠ってしまう。主要な政治家は殆ど死んでしまって、周りは世代の違う若造ばっかり。その中で、富子は一人で幕政と都の建て直しに奔走するわけです。
そこで彼女がやることが、京の七口といって京都の出入り口に関所を置く。そこで交通税をかけてしまう。当然それは庶民の反発を買うわけですね。特に山城の国の商人たちは、いろいろな商品を持って京都にものを売りに行ったり、逆に物を買って帰ったり、その度にその品物にも税金をがかかる。ですから、関所撤廃の一揆を起こしたり、富子に反抗したりする。後年富子が悪女と烙印を押される原因は、この辺りに集中してるんです。『大乗院寺社雑事記』という坊さんたちの日記で、“前代未聞のことなり”みたいなことで、富子の悪口を書きまくるわけですね。富子が悪女だったというのは、この辺りから定着するわけです。
放送が始まった初めのころ、日野富子は悪女だというので、期待して観たんだけど、以外に悪女でもなんでもないんじゃないかと言われたりしたんですけど、富子が悪女と言われるのは、実はこの時からで、応仁の乱以降から実は悪女なんです。以前は悪女でもなんでもないんです歴史上は。だから、富子が悪女でないことに失望していた方々には、この辺りからそのイメージにかなう悪女ぶりを発揮するわけなんですけど(笑)。
経済復興がある程度なってから、富子のほんとうの黄昏期が訪れるんですね。つまり、義尚が病死してしまう。次の将軍をきめなきゃならないという時期から管領政元など新しい世代が、幕府の実権を握り始める。そういう若い指導者にとっては富子も義政も、邪魔なんですよね。彼らがなんとか富子を疎外しようとする。そうこうしているうちに義政も死んでしまう。義政が死んで一週間目に富子は尼さんになるんです。尼さんになって、義政のそれまで暮らしていた東山山荘、今の銀閣寺に移り住んでそこで夫の菩提を弔って静かな余生を過ごそうと思っていたけれど、やっぱり将軍継承問題に巻き込まれて、なかなか心穏やかな日々が過ごせない。結局細川政元が、明応の政変と呼ばれるクーデターを起こして、富子側が決めていた将軍・足利義材という将軍を追い落として、堀越公方という鎌倉のほうにいる公方さんの息子、清晃を勝手に将軍に擁立してしまったりする。で、同時に富子を銀閣寺から追い出してしまう。もうその辺になると、富子というのは全く孤立無援の骨董品扱いみたいになってしまう。それ以後の富子は、いったい何処で死んだのか何で死んだのかも不明辞世の歌一つ記録にはない。完全に世の中から忘れられてしまうんです。
最後の一言に向かってドラマは進む
富子も主人公として愛せるなと思ったのは、もう間もなく死ぬという義政に富子は、“あなたあっての私だったのだ”と述懐するという記録があるんです。今まで将軍継承のことや息子のこと、政治のことで夫婦喧嘩ばっかり重ねてきたけど、その自分は、あなたがいたからこそ自分もそうやって、あなたと喧嘩するような立場にいられたんだと述懐する。富子が夫に対して優しい言葉をかけたただ一つの記録なんですね。この一言で富子は許せる。少々夫婦喧嘩をしても夫を欺いてもこの一行が史実としてあるならば、大丈夫だと思って書いていったんですけどね。
どんなドラマづくりの時でもそうですけど、行く先も目的もはっきりしない船出をする時でも、ドラマの場合には最後の一言、納得のできる言葉が見つかれば、その一言に向かって、航海をしていくことが出来るんです。『淋しいのはお前だけじゃない』というドラマを書いた時には、ドラマを書き出す前に“いい夢見たなあ”と言わせようということを決める、その“いい夢見たなあ”の一言のために、全部のドラマを動かせる。座標、それが羅針盤になるわけです。今度の『花の乱』では、“あなたあっての私だったのだから”というその一言に向かって走ったんです。
最終回で完結しなければならないのは、夫婦の別れ、富子の故郷である山城の国・椿の庄との別れ。そこから富子のさまよいが始まる。大河ドラマの主人公というのは、同時に悲劇の主人公でもあるのですけど、富子の悲劇性というのは、すべての実権を失い、人生の敗北者となってもなお生きつづけなければならなかった悲劇なんですね。富子自身がどうやってその孤独の魂を救うのかが、ドラマの課題でもあったんですけど、書いてる時はその結論までは出せないままで書きつづけたんです。いざ、最終回を書き出して義政が死んでいく、富子が見取る、山城の国が政元たちの手によって壊滅させられる。
全てを失っていく富子は、ふっと自分の命は自分一人のものではない、ということに気付くんです。自分の命の中には、生涯で出会った様々な人々の魂が宿っている。だから自分はまだ死ねない。自分が死んでしまえば、自分の中に宿っている多くの人々の魂も本当に死んでしまう。義政も宗全も勝元もすべての人が自分が生きてる限り彼らも生きている。自分は一人ではない、自分の中のあの懐かしい人と共に生きつづけていくんだというような境地にたどりつくわけです。
富子は五十五歳で死ぬんですけど、それから三年後に管領政元も家臣の手にかかって暗殺される。それを契機に、世の中が戦国時代に突入していく。全く収拾がつかなくなる。天下統一をめざす織田信長が上洛して、その時の十三代将軍足利義輝に謁見をするのは、それから五十三年後です。政元が死んで五十三年後に信長が京都に上ったといえば、ああ富子の時代は歴史のどの位置にあったのかというのが、大体お分かりいただけると思う。この辺りの混乱が、群雄割拠の戦国時代を招いたんだなあということが。
書き終えたあとで
振り返ってみますと、『花の乱』の第一話を書き上げたのが、去年の十月二日だった。最終回を書き上げたのが、九月の二十九日です。だから、ちょうど一年間書きつづけた。
全部書き上げて、どの作品にも悔いはないかと聞かれたら、一本だけあるんですね。一回目の脚本です。これは詮ないこととはいえもう一回書き直していいと言われたら、第一回目は書き直したいですね。何でと言われたら、一口で言えば、一回目の一話に収める情報量が多すぎたんです。つまり、あれもこれもと詰め込み過ぎた。それを書いた当初は書いた本人も演出もプロデューサーも、非常に気にいってくれて、これでいけるみたいなことだったんですけど、つまり僕も含めてみんなが、室町時代というものの魔力に幻惑されたんですね。とり憑かれてしまった。しかしわれわれはそれより半年前から室町にのめっていったわけですから、ほぼ室町時代の空気も飲み込んだ上で書いた。読む方も一応その知識を前提に読みます。
観てるお客さんにとって、室町時代というものは、われわれが想像した以上に縁遠いんですね。平安時代より勿論戦国時代より馴染みが薄い。出てくる登場人物に関しては、主人公の日野富子を含め殆どが知らない。なんとなく名前を聞いたことがあるのは頓智の一休さんくらいで。金閣寺と銀閣寺と一休さん、この三つしか知らない人たちに向かって我々はドラマを作るんだということを、もうちょっと考えたほうが良かったかなと。だから、第一回目は、伝えるべき情報量を半分くらいにしても、一つ一つをもうちょっと丁寧に描いたほうが良かったかなと。だから、第一回目は、伝えるべき情報量を半分くらいにしても、一つ一つをもうちょっと丁寧に描いたほうが良かった。夢幻の世界い導くにしろ、二人の富子の話をなぜこの設定にしたいかということを伝えるにしても。具体的に言うと、富子の時代以前の話まで入れたんですね。義政の親父が家臣に暗殺された嘉吉の変というんですけど、そういう事件まで情報として入れてしまった。そうすると登場人物が多すぎるんですね。しかもこれが信長や家康が出ていればいいんですねが、まず出ている人物に関しては誰も何も知らない。そういう設定のわりには、やっぱり一回目に出した人間の数が多すぎた。わかりやすく面白くということは、それでも相当に配慮したつもりだったんですけど、振り返れば、あの一回目だけはもう一回書き直したい。
室町という時代は魅惑的な世界でしたね。歴史ドラマに興味のある人は、ビデオに録って何回でも見るらしい。そのかわり見ない人は全く見ないみたいな、視聴率を極めて厳選してしまいました。
それに関しては悔いはないんですよ。室町をやると決めた以上は、室町と心中する気でなければ、戦国時代のようにも江戸時代のようにも作れない。つまり空気が全く違う。その空気を醸しだすには、これだけのめり込まなきゃ無理だったと思いますけどね。だから最初のスタートからまさに狙い通り、中身も方向性が非常にはっきりしてましたから、スタッフキャストの団結力はきわめて強かったですね。意図から外れるとか誰かが勘違いしてるとか、いうのがない。極めて確信犯的な共同正犯のもとに(笑)一致団結して突っ走った。こういう大河も珍しいと思いますね。だからやった意義はあった。
一番最初の頃に言ったと思いますけど、狙い通りに中身がいったということも、含めてなんですけど、まさに作る人間が誇りを持って、作れるものを目指したいと。それはその通りになりましたね。
毎回そうですけど、最後の原稿に『完』という字を書きおわったときには、しばらくボーッとしてね。夕方の五時頃だったんで、それをFAXで送った後に、三日くらい風呂に入ってなかったんで、ゆっくり風呂に入って、ふわ~んとしていた。夜、八時くらいからプロデューサーとディレクターがお疲れさまを言いに来てくれて、近くでとりあえず乾杯をした。ほろ酔いで表へ出たら、台風の余波で、風がもの凄くひどくて並木が踊るように揺れてるんですね。それがまた凄くここちよくて、ああこの一年の見返りはこの瞬間かとほんの僅かですけどちょっとだけ幸せな気分になって、あとは泥のように眠りこんでしまいました」
――一年間やってきて、特別の気分でしょうね。
「なんか悲しい気分ですね。嬉しいとかホッとしたとか、あんまりそんなこともなくて、でも、これは大河に限らないですね。長いシリーズの終わりのマークを書いた時というのは、淋しい気分になるだけですね。あの晩はちょっと誘いだされたおかげで、一人で帰ることが出来て、その時だけでしたね、風に木が踊ってるのを見て、ああなんて綺麗な夜だって。それまでは、文字通り雨が降ろうが槍が振ろうが、『花の乱』のことしか頭になかったわけですから、久しぶりに風を感じたり、からっぽの気分で自然を見つめることが出来た。でもこういう気分も、まあ気持良く一年間トラブルもなく思い通りのことを書かせてもらった結果なんでしょうね」
おわり
※ 月刊ドラマ閲覧室は、(株)映人社のご厚意により、5回連載の「『花の乱』創作ばなし」を当サイトに転載させていただきました。