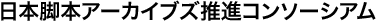デビュー作『快獣ブースカ』の後、『ウルトラセブン』から、若き頃の市川森一にプロデューサーとして向き合った橋本洋二。脚本家のスタート地点のもがき苦しむ姿や心模様はどうだったのか。市川脚本の原点がここに明かされる。
【出会いのきっかけは、妹の由実子さん】
――橋本さんは『ウルトラセブン』の途中からTBS側のプロデューサーになられて、そこで初めて市川さんと知り合われたのですか?
市川君の妹に由実子さんというのがいて、ユミと森一とぼくの3人で、ぼくの作った長崎のラジオドラマを一緒に聴いたのが最初でした。山岡久乃さんが主演で原爆被爆者の怨念みたいなものを綴ったドラマでした。
ユミはTBSのアルバイトをしていて、そこの場所に僕も出入りしていて知り合いだったものでね。職場でユミが、自分の兄がこれからテレビの作家になろうとしていると言ったようです。それで周りの方が「橋本さんと一回お会いしたら」みたいなことで、間を取ってくれました。長崎の出身だっていうし、あまり広くはないラジオの編集室でしたが3人で聴きました。
【『コメットさん』の後半から参加】

――実際にプロデューサーと脚本家の関係で一緒に仕事を始めたのは『コメットさん』からですか?
そうだね。『コメットさん』みたいなのが割と合うのじゃないかと勝手に思って、「書いてみないか」と言ったら、「喜んで書かせてもらいます」というご返事だったので、「それじゃあ、1本書いてごらんなさい」となった。『コメットさん』もカラーになってからの話だね。
――第50回「アリの国探検旅行」。主人公の兄弟二人がアリと一緒に巣穴に入っていって冒険するという……
そうです。コメットさんの魔法で極小化した兄弟がアリに導かれて、母親が落っことしたダイヤモンドを見つけるという話でした。
――コメットさんは住み込みのお手伝いさんで、その家には2人の男の子がいました。その2人があんまり勉強もしないし、親の言うことも聞かない子どもたちで、その子どもたちをコメットさんがいろいろな形で鍛えるというのが物語の骨子になっていました。当時の子どもは「現代っ子」と呼ばれていて、何の苦労もなく、悪く言えばぬるま湯のような状況でぬくぬくと生活してるから、そういう子どもたちにある種試練を与えて、それを乗り越えることで一段成長させる方がいいということを『コメットさん』の中でも……
それがテーマでした。番組を企画した脚本家の佐々木守とは、彼が学生時代からの付き合いだったからね。現代っ子の頭をポンと打つみたいな、そういうことを『コメットさん』を通して貫いていったらどうかで始まったんです。
――市川さんは50話から参加して、全部で11本書いていますが、市川さんの書いた『コメットさん』は、橋本さんが言うテーマとはちょっとずれていて、コメットさんの恋愛話とか……
そう、あんまりぼくや佐々木君のいうような脚本作りとかテーマとかを押し付けても、作家はなかなか書けない。だから、視聴率も安定してきたことだし、門戸を開放していろいろな人を自由に取り入れてやったらどうかと思いました。特に若い人で、こういうものを書きたいという人がいたらどんどん書いてもらおう。登竜門みたいになればいいんだよと思いましたが、でも結局、市川君くらいかなあ。やや無名に近い作家が書いて、何本も書けたというのは。
――その次が「怪奇大作戦」。これは円谷プロにとっても「ウルトラマン」や「ウルトラセブン」の巨大ヒーローで日曜よる7時の武田アワーをずっとやってきたのですが、巨大ヒーローじゃない路線を模索してた時期の中で円谷プロとTBS担当の橋本さんとで企画の段階から練ったということですか?
『怪奇大作戦』の企画には市川君は参加していなくて、金城哲夫さんとやったんだ。だけど、金城さんはその頃、フジテレビの『マイティジャック』で忙殺されて時間もありませんでした。電話で話したりしていましたが、彼が書いてきたものとぼくの考えと違うので、佐々木(守)君が最初書いたものがリード役となりました。
――市川さんは『怪奇大作戦』で3本だけ書いています。
市川君にとってもこれは、本意なホンじゃなかったのでは。脚本の上原正三さんがその路線のことを非常によくわかってくれたんだよね。それで上原に引きずられてというか、上原が自分の後輩でもあるし、一緒にやってみないみたいな感じで、一緒にやったと思うんです。だから、市川くんが書いたものについての脚本作りには私はあまり関わってはいないんですよ。
【『胡椒息子』で母親の存在への感情移入】
――そのあとは、『コメットさん』と同じブラザーミシンの枠で『胡椒息子』。これは市川さんが初めて全話を一人で書いていますね。

主人公はお妾との間に生まれた少年で、新しいお母さんが来て一緒に暮らしているんだけど、そりが合わない。さみしい思いを抱えながら学校へ行っている。そのさみしい思いをしている少年が母の面影を浮かべながら、それを心の支えに生きている。最終回で生みの親であるお母さんと会わせるか会わせないかということで、ぼくと市川君で意見が食い違ったんだ。市川君は、実母と会わせなくてもいいと。だけどぼくはこれは会わせなくてはいけないと。獅子文六の原作でも会うことになっている。
――実は市川さん、最初に書いてボツになった原稿を持っていて、それには、冒頭で少年が夜うなされているんですね。夢を見ている。その夢は、血まみれになった青年が夢に出てきて、とても苦しそうな顔をしている。だけど、なぜ苦しいのかは聞いても答えない。どうやら、それは自分の未来の姿だと。そういう出だしなんです。
思い出したなあ。
――それで、産みのお母さんが現れても再会もせず、最終回も自分の未来の姿、血まみれの自分が出てきて、暗澹たる気持ちで終わるんです。
市川君らしいやり方だねえ。つまりね、ここに至るまで彼は自分の書きたいものが書けないで悶えてたんだろうと思いますよ。いろんなものに縛られてますから、原作者である獅子文六と親しい人がその当時代理店の博報堂にいて、その人がいろんなことを言ってきたんです。それでは、監修者に八住利雄さんを付けましょうと。そうしたこともあってね、がんじがらめに縛られていたんですよ。それで大映のプロデューサーと相談して印刷までして、スポンサーなどの反響をうかがった方がいいと。細かい事情は彼には話さなかったけれども。彼としても不本意なうちに終わった。自分の力の発揮場所がなかったと言ったら悪いが、自分のイメージが通らなかったものだったろうと思いますね。
――でも全話任されたわけだから、最初は市川さんとしてはかなり意気込んでいたはずですね。
こんながんじがらめな中で書くとは思わなかったでしょう。最終回は結局、いまお話した台本がキャンセルになり、お母さんの来ている部屋に、少年と仲の良かったお手伝いさんに手を引かれて、「お母さんが来ているから顔だけ見なさい」と連れてこられるんですけど、少年は拒否して、障子越しにお母さんの影だけ見て帰ってくる。
少年の自立みたいなことをひとつのテーマに書きこみたかったんだろうと思うから、まあそこぐらいまでかなと。
――市川さんとしては精いっぱい妥協してその形になったんですかね。
そうね、ぼくらもね……。
――その後の市川さんのドラマを見ても、いわゆる母と子の愛情をあたたかく描いたドラマって少ないですね。その点は作家として自分の作風をコントロールできなくて、母親を描くときはどうしても原体験というものに引っ張られて書いてしまう。だから当時大全盛だったホームドラマ書かなかったですね。石井ふく子さんのドラマも市川さん、誘われなかったですね。
彼も書かせてくださいという気にはならなかったんじゃないですか。ぼくと書いた中で、母親が大きな役割を果たすってものはないでしょ。ないはずですよ。それは触っちゃいけないなと、避けてましたけどね。
――でも脚本家って、ある種の挫折というか、そういう激しい感情や体験を持っていないとできない商売だという気もするんですけど、どうなんでしょうか?
どうかなあ、人によるんじゃないですか。そういうものがあっても、それを超越して書く人も当然いるでしょうねえ。そういうものがなくてもどんどん書ける人もいるし。それは作家に聞いてみないとわかんないなあ。僕は、そういう原風景がないと書けないということはないと思います。ただ彼の場合、原体験を聞けば聞くほど、やっぱり触っちゃいけないなという気がしてましたけどね。
――だから後年、市川さんはそういう自分の中の拠り所であり、束縛でもある原体験をかなり意識していました。橋本さんと作っている頃は多分そういうものがストレートに出てしまったと思うんですけど。もう少し経験を経ていくと、そういう自分の原体験もある程度コントロールしながら母と子のドラマなんかも書けるようになっていきますけど、やはり何かしらつながりがあって、原体験に引きずられていたフシはありますよね。
彼はそういう性格でしたね。そういうもの簡単に捨てちゃう人はいますよね。彼はそういう中からひとつの自分の、怨念って言っちゃわるいけれども、そういうものを作り上げてそういう中で書いていくというタイプでしたね。
【「ウルトラマンA」最終回の話】
――そのあとはまた、『彦佐と一心太助』『千葉周作・剣道まっしぐら』とシリーズの途中から市川さんが書いていますが。
ひまだったら書いてみないというのがずーっと続きますね。『帰ってきたウルトラマン』も彼は企画に参加してないから。『刑事くん』も『シルバー仮面』もそうですね。企画を彼とやったのは、ずーっと行って『若い先生』かな。

――その前に「ウルトラマンA」があります。『ウルトラマンA』は、市川さんは企画から参加され、最終回も書いていますけど、最終回でウルトラマンAは星に帰るわけですけど、そのときにテレビを見ている子どもたちにメッセージを残しますよね。有名な「何度裏切られてもやさしさを失わないでくれ」という。あれは市川ドラマの中でも名ゼリフとして語られてるくだりなんですけど、あの最終回の脚本作りのご記憶はありますか?
彼には、「思うように書けばいいから」と。終わりはこうしたいということ、それでいいんじゃないのと。星に帰ろうが、地球の中で死のうがかまわない。あなたが作ったシリーズなんだから、あなたが最期を見届ければいいと言いました。そういう枠じゃないですか。気楽に出来る。スポンサーの枠もないしね。「A」もなんとかまあまあの視聴率で終われたしね。
――『ウルトラマンA』の設定というのは、男と女が合体してヒーローに変身するというのが当時斬新だったわけですけど、これはいろんな意味があるようで、よく言われるのは、市川さんはクリスチャンだから三位一体じゃないけど男女合体で超人になるという考え方が出てきたんだと。最終回のセリフに「裏切り」という言葉を入れたのもクリスチャン的な発想だと言われるんですけど。市川さんの中のクリスチャンである部分は、プロデューサーからご覧になって、市川さんの脚本を読んで、感じることはありましたか?
いや、まったくないですね。いろんな話は市川君から聞いて、経済的にも精神的にもたいへんな苦労をした人だということは知っていましたけども、それを表に出してラジカルに書いたってものはないですよ。やっぱりそこは彼の力だね。そういうものをガリガリ書こうという人も多いけれども、やっぱりそれを抑えて書いていたんじゃないですか。
幼い頃とか学生時代のこととかね、ずいぶんいろんな話聞きましたよ。それなりに苦労してきた人だし、それなりにいい加減なところもある人だった。ぼくはわかってましたから。その辺は彼とは気脈が通じるというのか、わかりあっていたように思いますよ。
【プロデューサーVS.脚本家】
――プロデューサーと脚本家の関係でいうと、テレビドラマに対する基本的な考えの違い、一致点はあるんでしょうけど、脚本作りではどうですか。その中で意見がぶつかりあうことも当然あったと思うんですけど、例えば『刑事くん』に沢田研二が出たときに……
最後は、彼の脚本では、犯人役のジュリーはナイフを投げ捨てないということだったんだけどね。刑事に追いつめられて「俺の負けだよ」ということをぼくは具体的に示したいんだけど、市川君はそれに「これは勝ち負けの話じゃないんだ」と抵抗したんですよ。これも最終的には双方歩み寄って、沢田研二が抜き出したナイフをポンと海に投げ捨てるという形にして、“着地”しましたね。

――こういうときって、出来上がってきた生原稿を橋本さんが読んで、「ここがちょっと違うなあ」とディスカッションするわけですね。そうすると市川さんは素直に聞くんですか?
ぼくが付き合っている大概の作家は素直に「はい、そうですか」とは言わないよ。だって、それだけのものを書いているわけだから。また、それだけのものを書く人でないとぼくは付き合わないから。それでどういうふうにするかと、延々打ち合わせが続くわけだ。
――そういうときって橋本さんは、自分の思いどおりに相手を説得しようとするのか、妥協点を探りながら話していくのか。あくまで自分の考えを押し付けるわけではないですよね。
まあ最後まで説得し続けたものもあるし。途中で「そうか、そう思っているならこういう解決の仕方をしたら」と言うことはあるしね。そういう意味では、ジュリーのものなんかは割とぼくには印象に残ってますけどね。
――市川さんとお酒を飲まれたりすることはあったのですか?
打ち合わせが終わった後に酒を飲むのは毎回でした。それでその場所で多少ケンカ気味になったり、いろいろしましたね。脚本上のことは仕事の席で終わっているから、そこでは「テレビとは何か?」「ドラマとは何か?」「その中で自分たちは何をするか?」とか、そういうことだね。「テーマはなくてもドラマはできます」と泣きながらずいぶん言っていた。「それはえらいね」なんて馬鹿にするものだから、彼は余計怒って。そう言いながらも、彼はテーマを作って書いているんだよね。
――橋本さんは初期の頃の市川さんを形作っていった人の1人というか……
それは結果論でそういうふうに言われるのかもしれないけど、作家を育てようとか、そういうことはなかったですよ。大体、脚本家って育てるもんじゃないでしょ。みなさん、どう考えてるか知らないけど、育てて育つもんじゃないと思うんですよね。練習したからうまくなるとかね、そういう類いじゃなくて、やっぱり自分の持ち物とどう勝負していくかということじゃないかと思うんですけどね。そういう意味では彼は、お母さん亡くなっているとか、積み重ねてきた苦労がすごく役立っているように思いますね。
――『刑事くん』の第4部を最後にして、市川さんは大人向けのドラマの方に活動の場を移していくんですけど、子ども番組から離れたっていうのはどういうことだと思いますか?
それは彼が力があるからですよ。子ども番組を軽蔑するわけじゃないですよ。でも、そういう時間帯でも書きぬけるものを持ってたんでしょう。内側にも持っていたし、筆力もそれだけのものがあった。脚本を書きぬく力があったということじゃないですかね。
最初のうち、1時間ドラマ書いたけど、あんまり成功したものはないんだよね。だんだん積み重ねていくうちに良いものができるようになっていったと思いますね。
――市川さんを「シンイチ」と呼べるのはそう何人もいないですよね。やっぱり若い頃、その初期を知っているプロデューサーと新進作家、若手作家の関係だから。それだけのプライベートな付き合いもあったのだろうし。
まあね。そういうふうに付き合ってきたから。「シンイチ」っていうのが、いまや「市川先生」と言わなきゃいけないだろうし。まあ電話でよくケンカしてたのを、死んだ女房がよく知ってますよ。
(2012年11月8日、東京・新宿にて/取材=加藤義彦 文=三原治)
 橋本洋二氏 略歴
橋本洋二氏 略歴
橋本洋二(はしもと・ようじ)
1931年、4月生まれ。東京教育大学卒業後、TBSに入社。ウルトラシリーズは『ウルトラセブン』の2クールめから参加。テレビ作品担当前はTBSラジオでラジオドラマやドキュメンタリーの制作に携わる。ウルトラシリーズ以外では、『柔道一直線』『刑事犬カール』『妖術武芸帳』など多数。
市川作品では、プロデューサーとして、『ウルトラセブン』『コメットさん』『怪奇大作戦』『胡椒息子』『彦佐と一心太助』『千葉周作・剣道まっしぐら』『帰ってきたウルトラマン』『刑事くん(第1部~第4部)』『シルバー仮面』『ウルトラマンA』『熱血・猿飛佐助』『若い!先生』を担当した。