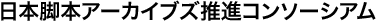市川森一はNHK大河ドラマ、東欧ロケを行なった長時間ドラマほか、数々の大作にも参加した。その企画者である近藤晋プロデューサーに、番組の制作秘話を語ってもらった。
【出会いは『黄金の日日』】
――市川森一さんが初めて手がけたNHKの大河ドラマが『黄金の日日』です。その企画者が近藤さんですね。
はい、そうです。当時の私はNHKの局員で、テレビドラマの企画、制作を手がけていましたが、1978年に放送される、第16作目の大河ドラマを担当することになったんですね。確かぼくは当時47歳で、大河を担当するのは、これが初めてでした。ぼくの信条は「他人のやらないことをやる」なので、歴史ドラマである大河を作るにあたっても、新しいことに挑戦しようと考えたわけです。
――『黄金の日日』は戦国時代の堺を舞台にした話で、主人公は商人でした。
ええ。市川染五郎さん、現在の松本幸四郎さんが演じた主人公の呂宋助左衛門は、貿易都市の堺で活躍する商人でした。それまでの大河は武将が主人公だったので、あえて庶民を主役に選んだわけですね。
『黄金の日日』がそれまでの大河と異なる点が、ほかにも二つあるんです。一つは初めて海外ロケを行なったこと。撮影場所はフィリピンでしたね。もう一つは、原作と脚本を同時進行で作ることでした。
それ以前の大河は、最初に原作となる歴史小説があり、それに沿って脚本家がシナリオを書いていました。しかし、『黄金の日日』ではその方法をやめて、作家の城山三郎さん、脚本の市川森一さんにお願いして、同じ設定を使って物語を作るようにしたんです。経済全般に詳しい城山さんには、「経済」の視点から戦国時代を描いてもらい、それを小説として発表する。市川さんにはドラマのシナリオとして書いてもらうと。お二人に、それぞれの『黄金の日日』を作ってもらおうと考えたわけですね。
【大河ドラマ初! 原作小説を使わない『黄金の日日』】
――当時の城山さんは第一線で活躍する小説家でしたが、市川さんはまだキャリア10年の脚本家でした。その市川さんに、なぜ脚本を頼んだのですか?
先ほども申し上げたように、『黄金の日日』では、まだ誰も試みていないことをやりたかったから、脚本も新鮮な感性を持った若い人に書いてほしかった。初対面で「大河ドラマを書いていただきたいので、2年間身体を預けてください」と言いました。場所はNHKの食堂です。市川さんはしばし無言。「ぼくでいいんですか」が第一声で、ぼくは「名古屋のドラマの気持ちのままで。どうぞ是非」と答えました。

――その「名古屋のドラマ」というのは、1974年放送の『黄色い涙』ですか?
そう、『黄色い涙』です。その後、市川さんとは長い付き合いになりましたが、彼によると、初対面のときにぼくは下駄を履いていたらしい(笑)。そんなはずはないんだけど、こんな大切な話なのにざっくばらんな姿勢だったんで、そういう印象が残ったんでしょう。この時、我々は信頼関係で結ばれました。
――登場人物の設定やストーリーはどのように作ったのですか?
最初に城山三郎さん、市川さん、そしてぼくの3人で、丸の内や四谷の宿を転々として、アイデアを出し合い、密かに全50回の構成を練りました。
打ち合わせの結果、物語の中心人物は助佐衛門と、彼の幼なじみである石川五右衛門、善住坊の3人とし、彼らが戦乱の世を生き抜くなかで、信長、秀吉といった当時の有力武将と関わるように描こうと決めたんです。中心人物となる3人は、みな実在した人物ですが、彼らについて書かれた文献は少ししか残っていないから、我々の方である程度、自由に描くことができました。『黄金の日日』という素晴らしい番組名は、城山さんが付けてくれたものなんですよ。
それから城山さんは大綱と男の登場人物、市川さんは台詞と女の登場人物を描くという、大まかな担当も決まりました。市川さんが考案した人物は夏目雅子さん、竹下景子さん、名取裕子さんといった当時の若手女優が演じてくれましたが、彼女たちは、その後も市川ドラマの常連になりましたよね。
――物語の中心人物となる3人は配役が絶妙でした。助左衛門を演じたのが歌舞伎界の若きエースだった松本幸四郎さん。天下の大泥棒と呼ばれた石川五右衛門は、状況劇場の看板役者だった根津甚八さん。そして射撃の名手である僧侶の善住坊は、東映の悪役俳優として有名だった川谷拓三さん。
根津さん、川谷さんは当時のテレビ界ではほとんど無名でしたけど、この役に賭ける執念が伝わったのか、放送が重なるにつれ二人の人気が高まりました。五右衛門も善住坊も最後に処刑されますが、視聴者から嘆願の手紙が山のように来ましてね。「二人を殺さないで」って。そこで市川さんと相談して、二人の処刑を先に延ばしたんですよ。
――当時のいわゆるアングラ演劇のスターだった唐十郎さんが、人買いに手を染めた貿易商としてゲスト出演しましたね。唐さんは市川さんにとっても憧れの存在でした。
ぼくも唐さんが作る芝居が好きだったから、唐さん率いる状況劇場の根津さんと、唐さんの当時の奥さんだった李礼仙さんにレギュラー出演してもらったんですよ。李さんの演じた役の名前は「お仙」でしたが、これは彼女の当たり役で、状況劇場の人気演目だった「腰巻きお仙」から頂いたものです。
――大河ドラマは1年間の放送で、回数も50回ほどありますが、市川さんの脚本執筆ははかどりましたか?
市川さんにとって一人で50回分の脚本を書くのも時代劇も初めてだったし、苦労もあったでしょうが、スランプに陥って筆が止まることはなかった。ただし筆は遅かったですね(笑)。大河ドラマは制作のスケジュール上、脚本家には、1週間に1話分を書き上げてもらわないと困るのですが、市川さんはいつも1話分書くのに、10日はかかりました。
〆切りに間に合わないときは、原稿をもらいに彼の自宅へ行きましたよ。あるとき夜中に訪ねて、いつも通り1階の居間で原稿を待っていたけど、なかなか彼が2階の書斎から下りてこない。書斎は寝室の奥にあると、市川さんから聞いていたので、しびれを切らしたぼくは、2階へ上がって寝室のドアをそっと開けたら、白いネグリジェが目に飛んできた。びっくりしましたよ、あのときは。夫人の美保子さんがベッドで寝ていたんですね。あとで市川さんが「何も寝室まで覗かなくても……」と呆れていましたけど、それくらい原稿が早くほしくて切迫していたんです。
大河ドラマは毎回、4、5名のディレクターが交代で演出しますが、書き上がった脚本に対して、それぞれの見方や意見があります。そうした声がすべて市川さんの耳に入ると、彼も混乱してしまう。そこで「脚本担当デスク」を作って、ディレクターたちの提案や不満は、まずその人に聞いてもらい、そのなかから選択した意見だけを市川さんに伝えました。脚本家には持てる想像力を十二分に発揮してもらい、自由に書いてほしい。その自由を確保することもプロデューサーの役割なんですよ。
【賛否が分かれた2度目の大河ドラマ『山河燃ゆ』】

――『黄金の日日』は、終わってみれば平均視聴率が25.9パーセントで、それまでの大河ドラマでは3位の好成績でした。近藤さんはその後、1984年の大河ドラマ『山河燃ゆ』で再び市川さんと組みました。
このときも流域を拡充しようと思って、大河で初めて昭和を描いたんです。山崎豊子さんの書いた小説『二つの祖国』を原作にしながら、太平洋戦争当時にアメリカで暮らしていた、日系人たちの姿を描いたんですね。
ところが、事前に現地で日系人の皆さんに会って取材したら、同じ日系人でも、一世と二世では、祖国に対する心情に違いがあるとわかったんです。日本で生まれアメリカへ渡った一世にとっての故国は日本ですが、アメリカ生まれの2世3世にとっては、アメリカへの忠誠心の方が強い。そうした微妙な心情のちがいに配慮しながら、市川さんには脚本を書いてもらったんです。
ドラマの主人公は日系人の天羽兄弟で、どちらも架空の人物です。松本幸四郎さんと西田敏行さんに演じてもらいました。アメリカでロケ撮影も行ない、日本のドラマでは初めてハリウッドのスタジオを借りて、リトル・トーキョーの町並みを再現したんですよ。
――放送を観た視聴者の反響はどうでしたか?
賛否両論ありました。当時は、太平洋戦争が終わって39年しか経っておらず、戦争の傷を抱えて生きている人が、日本にもアメリカにも数多くいましたから。それに大河ドラマは視聴率が高く、視聴者の数も多いから、いろんな反応があるのは仕方のないことなんですよ。
しかし『山河燃ゆ』の場合は、在米日系人を無用な摩擦に巻き込みたくない配慮から、アメリカでは放送中止という事態になりました。プロデューサーであるぼくは、番組を代表してあちこちへ出かけては、先方の意見を聞き、こちらの制作意図を説明したり、相手に誤解があれば、それを解くように努力したんです。
もちろん市川さんにも、そうした声はある程度は報告しましたが、なるべく彼には伸び伸びと書いてほしいから、脚本執筆の妨げになるような情報は伝えませんでした。
――脚本を書くなかで市川さんから要望が出たことは?
ありましたよ。ラスト近くで米軍と日本軍に別れていた兄弟が戦場で遭遇するシーン。幸四郎・西田両名優による見せ場ですが、その距離感で論議した時、市川さんは至近距離の対決を譲りませんでした。試写で見ると、このドラマの嘘がこのドラマの真実を強く訴えるシーンになっていたのです。
【東ヨーロッパで撮影した大作『ドナウの旅人』】
――近藤さんは『山河燃ゆ』の翌年にNHKをお辞めになり、制作会社に在籍しながらテレビドラマを作りつづけます。市川さんとの仕事もたくさんありますね。
ぼくが独立して最初に作ったドラマが『インタビュアー冴子』ですね(1985年放送)。このときぼくは、バラエティ番組を得意とする、IVSテレビ制作という制作会社でプロデューサー修行を始めたばかりでした。『冴子』は日本テレビへのデビューを祝って、市川さんが書き下ろしてくれたものです。

その後も市川さんとは『面影橋・夢いちりん』を作ったし・・・。あのドラマはほろ苦い青春へのノスタルジーを描いたもので、市川さんらしい作品でしたね(1988年放送)。『長崎異人館の女』は、市川さんの故郷である長崎が舞台でした(1989年放送)。ロケ撮影も現地で行ない、俳優さんたちにも長崎弁で話してもらったんですよ。
その次に一緒に作った『ドナウの旅人』は、特に思い出深い作品ですね(1989年放送)。作家の宮本輝さんが書いた同名の新聞小説をドラマ化したもので、2夜連続の前後編で、計4時間半もある大作でした。
――夫を捨てて逃避行の旅に出た母と、死に場所を探すその若き愛人、母を追いかける娘と、旅先で偶然、再会したその元恋人。この4人がドナウ川を下る旅をつづけるなかで、それぞれの気持ちに少しずつ変化が起きるさまが、じっくりと描かれました。
『ドナウの旅人』の原作小説はとても長いものですが、ドラマ化するにあたって市川さんは、特に麻生祐未さん演じる娘と、再会した彼女の元恋人との関係に目が向いていたんじゃないかな。ぼくが市川さんと組んだドラマや映画には、『精霊流し』『長崎ブラブラ節』など原作ものも多いですが、彼は原作小説を自分の俎板に乗せて脚本の主張もちゃんと味付けして料理する。その辺をよく知る達人でしたよ。
――『ドナウの旅人』はテレビ朝日が開局30周年ドラマスペシャルとして、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアの各テレビ局と共同制作した作品で、テレビ界初の東欧3ケ国でのロケ撮影も話題になりました。
ええ、ドイツのフランクフルトから始まって、ウイーン、ブタペスト、ブカレストと移動し、最後のロケ地が黒海の小さな村でしたね。撮影に入る前に、脚本作りのために、市川さんと一緒に現地を訪れました。
あのときのロケには思い出が多いですね。当時の東ヨーロッパは、ベルリンの壁が崩れる直前だったこともあって、政情が不安定だった。ルーマニアでは、すでに地元のテレビ局が反乱軍に制圧されていて、ロケの打ち合わせをしたいのに建物に入れてくれなくてね。懸命に説明したら、ようやく責任者が玄関先まで来てくれて、そこで打ち合わせをやりました。
ルーマニアとブルガリアの国境では、長い橋が封鎖されて通れなかった。しかもぼくらの乗った車に兵士が近づいて来て、いきなり車の床シートをはがすわけね、武器を隠してないか調べるために。緊迫した場面もありましたが当時、テレビ朝日にモスクワの大学を出たプロデューサーがいて、彼が水面下で撮影の許可取りなどをやってくれたおかげで、無事にロケを終えることができたんです。
【市川森一は気脈が通じた戦友】
――市川さんとの仕事は、2008年放送の日中合作ドラマ『月の光』が最後となりました。

晩年の市川さんは、小説執筆にも力を入れましたが、ぼくは長崎新聞に連載された『蝶々さん』を読んで「ぜひ単行本にすべきだ」と思いましてね。さっそく講談社の知り合いに声をかけました。それくらい魅力があったからです。
単行本の次は『蝶々さん』を映画にしたい、しかもアメリカで映画化したいと考えて、あちらへの売りこみの準備を始めました。ぼくは以前に『ミスター・ベースボール』という映画を日米共同で作ったこともあるので、アメリカにも知り合いがいたし、当時宣教師夫人として長崎に住んだコレルさんとお蝶の母と娘のような交情をまじえて組み立てれば、『蝶々さん』の世界は、あちらでも受け入れられるという確信があったんです。
ところがその準備中に、市川さんの急逝でした……。アメリカに頼んでいた『蝶々さん』の英訳本が届いた直後だったので、すぐ自宅へ駆けつけました。美保子夫人は、ベッドで静かに横たわる市川さんの顔前にそれをかざして「出来ましたよ、近藤さんが持ってきてくださりましたよ」と声をかけました。そしてそれを枕元において別室に去りました。「ごめんよ、遅れて」、ぼくは心で詫びて立ち尽くすしかありません。今もそのままです。何とか進展させなければ……。『蝶々さん』の映画化は、市川さんのためにも、ぜひ実現したいですね。
市川さんは、ひと言でいえば「戦友」です。ぼくにとって彼は、山田太一さんと並んで、最も大切な脚本家ですね。口はばったい言い方ですが、ぼくが志してきた「誰も試みなかったドラマ作り」……。そうした挑戦に、ぼくと一緒に真剣に取り組んでくれたのが市川さんであり、山田さんでした。
きっと市川さんとは気脈が通じたのでしょう。互いにひと言、ふた言話せば、気持ちが分かり合えましたよ。会えばいつも雑談ばかりで、真面目な顔で仕事の話をしたことはありませんでした。心がとても柔軟な人でしたね。
(2012年11月5日、東京・渋谷にて/取材・文=加藤義彦)
 近藤晋氏 略歴
近藤晋氏 略歴
近藤晋(こんどう・すすむ)
1929年、神戸市生まれ。学習院大学を中退後、劇団民芸の演出部を経て、1959年にNHK入局。番組企画者、プロデューサーとして、大河ドラマ『獅子の時代』ほか数々の話題作を担当。1985年に独立した後も、ドラマ『失楽園』、映画『陰陽師』ほか多くの人気作を世に送る。近作にドラマ『キルトの家』、映画『信さん・炭鉱町のセレナーデ』がある。
市川森一作品のテレビドラマは「黄金の日日」「山河燃ゆ」「インタビュアー冴子」「面影橋・夢いちりん」「長崎異人館の女」「ドナウの旅人」「往診ドクター事件カルテ」「精霊流し・あなたを忘れない」「月の光」、劇場用映画には「長崎ぶらぶら節」がある。